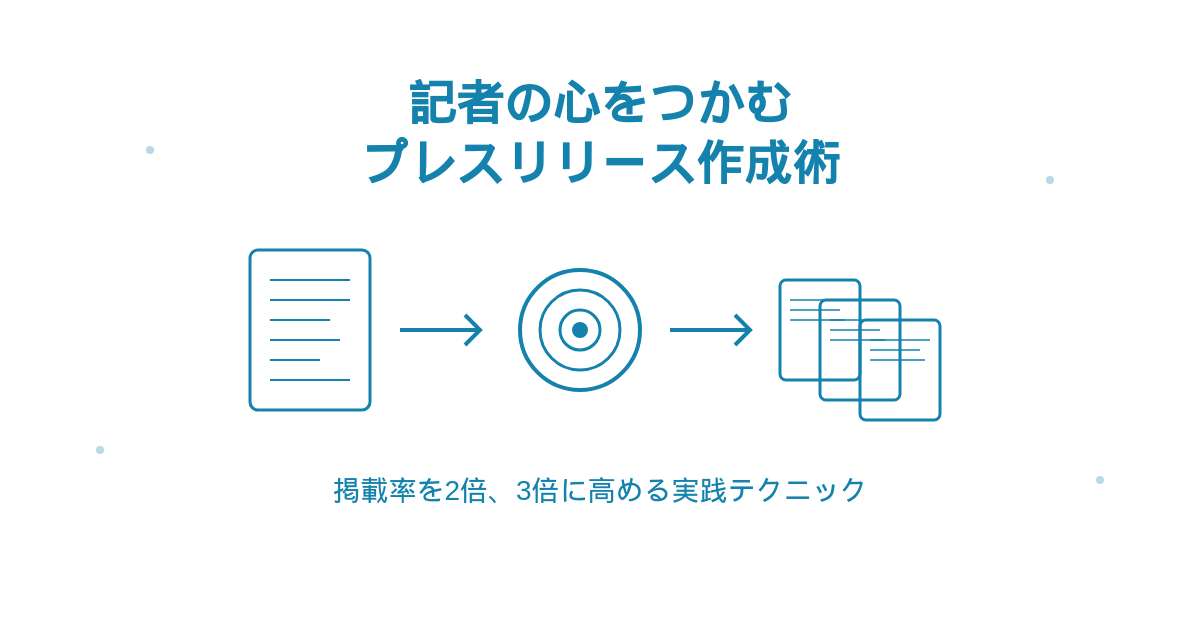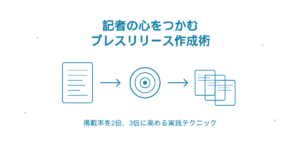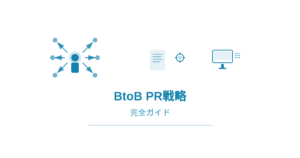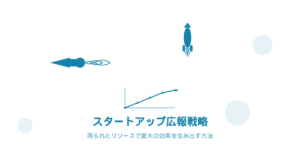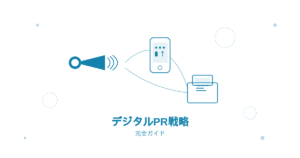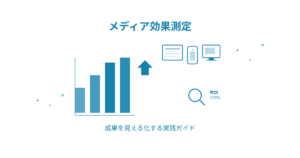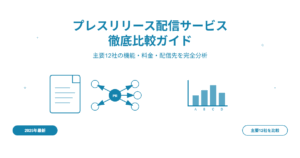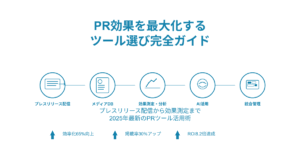「せっかくプレスリリースを配信しても、なかなかメディアに取り上げてもらえない…」そんな悩みを抱えるPR担当者は多いのではないでしょうか。実は、PR業界の調査によると、配信されるプレスリリースのうち、実際にメディアに掲載されるのはわずか10%程度という厳しい現実があります。かつて私も地域情報誌の記者時代、1日に100件以上のプレスリリースが編集部に届き、その大半が読まれることなく処分されているのを目の当たりにしてきました。
プレスリリースが埋もれてしまう理由は一体何なのでしょうか?そして、どうすれば記者の目に留まり、価値ある情報として取り上げてもらえるのでしょうか?
この記事では、メディア側と企業側の両方の視点を持つ私が、20年以上のPR業界の経験者から学んだ知見と、100本以上の記事執筆・取材経験をもとに、メディアの心をつかむプレスリリース作成と配信のコツを徹底解説します。「取り上げられるプレスリリース」と「スルーされるプレスリリース」の決定的な違いを理解し、明日から実践できる具体的なテクニックをお伝えします。
「自社の取り組みをもっとメディアに知ってもらいたい」「限られた予算でも効果的なPR活動を実現したい」とお考えの方に、特に役立つ内容になっています。最後まで読めば、プレスリリースの掲載率を2倍、3倍に高める実践的な方法が見えてくるはずです。まずは、記者が思わず取り上げたくなるプレスリリースの7つの要素から見ていきましょう。
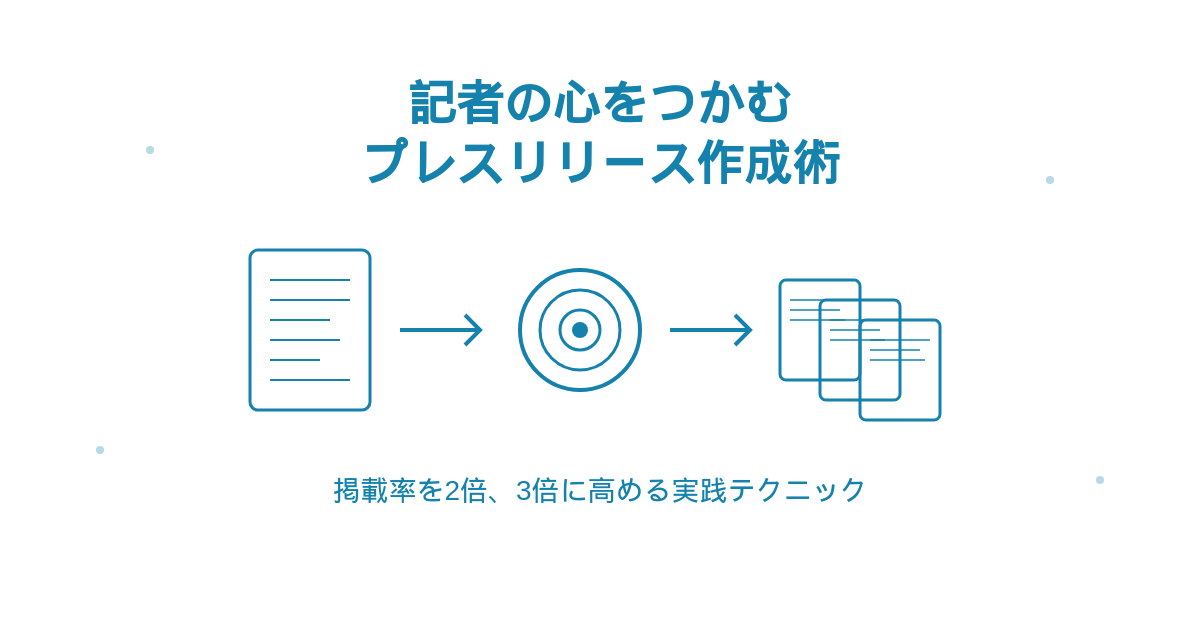
プレスリリースの効果を最大化する7つの要素
では早速、プレスリリースの効果を最大化する7つの要素を見ていきましょう。
1. 明確なニュース価値の提示
記者が最初に見るのは「これは本当にニュースなのか?」という点です。私が初めてプレスリリースを書いた時、会社の素晴らしさを延々と書いてしまい、肝心の「何が新しいのか」が伝わらない内容になってしまいました。ドキドキしながら送信ボタンを押したものの、案の定、一切反応がありませんでした。
ニュース価値とは「初」「最大」「唯一」「革新的」といった要素のことです。でも、ただこれらの言葉を使えばいいわけではありません。具体的な数字や背景情報と合わせて説得力を持たせることが重要です。
例えば、単に「新サービスを開始」ではなく「国内初、AIを活用した〇〇サービスで△△の課題を解決」というように、社会的意義や市場におけるポジションを明確にします。
ある食品メーカーのケースでは、新商品発表のプレスリリースを「糖質30%カット」という切り口から「働く女性の健康課題に着目した新開発製法による国内初の△△」と変更したところ、掲載率が3倍になった実例もあります。
2. データや具体例による裏付け
「へぇ、そうなんだ」と思わせるデータや具体例は、記者が記事を書く際の重要な素材になります。以前、あるスタートアップのプレスリリースで「革新的なサービス」と謳っただけで具体的な数値がなかったため、まったく反応がありませんでした。
その後、同じ内容でも「従来比30%の効率化を実現」「ユーザー満足度92%」といった具体的な数字を盛り込んだところ、3つのメディアから問い合わせをいただけたんです。記者の方からは「数字があると記事にしやすい」と直接言われました。
特に以下の要素は効果的です:
- 市場規模データ(例:「国内〇〇市場は2025年に△△億円規模に成長見込み」)
- 自社調査結果(例:「当社調査によると、回答者の78%が△△に悩みを抱えている」)
- 事例や体験談(例:「導入企業Aでは、業務効率が40%向上」)
- ビフォーアフターの比較(例:「従来の方法では2時間かかっていた作業が、15分に短縮」)
私の失敗談をもう一つ。以前、「画期的な技術」と書いただけで、なぜそれが画期的なのかの説明がないプレスリリースを配信してしまいました。案の定、まったく反応がなく、後日記者の方に理由を聞いたところ「具体的に何がすごいのか分からなかった」と言われ、反省したことがあります。
3. 社会的意義や背景の明確化
単なる自社製品の宣伝ではなく、「なぜ今これが必要なのか」という社会的背景や意義を伝えることで、記者の興味を引くことができます。
以前、ある環境技術の案件で、最初は「新素材開発」という切り口でプレスリリースを出したものの、まったく反応がありませんでした。そこで「2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題解決」という社会的背景を前面に出し直したところ、複数の環境専門メディアだけでなく一般紙からも問い合わせをいただけたんです。
社会的意義を伝える際のポイントは:
- 現在の社会課題との関連性(例:「高齢化社会における△△の問題を解決」)
- トレンドやニュースとの関連付け(例:「コロナ禍で増加した〇〇ニーズに対応」)
- SDGsなど社会的目標との関連(例:「SDGs目標12に貢献する取り組み」)
- 人々の生活をどう変えるか(例:「平均△△時間の削減により、家族との時間創出に貢献」)
私自身、かつては「製品の機能」だけを伝えるプレスリリースを書いていましたが、「その機能が社会や人々の生活にどんな影響を与えるか」という視点を盛り込むようになってから、明らかに掲載率が上がりました。
4. メディア別のアングル提示
同じニュースでも、メディアの種類によって注目するポイントは異なります。例えば、経済メディアは市場規模や収益性に、テクノロジーメディアは技術革新に、生活情報誌は実用性や身近さに興味を持ちます。
以前、あるITサービスのプレスリリースで失敗したことがあります。技術的な内容ばかりを詳述した結果、専門メディアには掲載されたものの、より影響力のある一般ビジネスメディアからはまったく反応がありませんでした。
その後、同じ内容でも「導入による経済効果」「働き方改革への貢献」「ユーザー体験の向上」など、複数の切り口を用意したプレスリリースに改善したところ、多様なメディアから反応をいただけるようになりました。
メディア別のアングル提示のポイント:
- 経済メディア向け:市場規模、収益性、業界影響度
- 技術メディア向け:技術的新規性、開発背景、既存技術との違い
- 一般紙向け:社会的影響、生活変化、トレンドとの関連性
- 業界専門紙向け:業界特有の課題解決、専門的詳細
あるクライアントでは、プレスリリースの最後に「メディア種別ごとの追加情報」というセクションを設け、各メディア向けの情報を整理して提供したところ、掲載数が2倍になったケースもあります。
5. 視覚的要素の効果的活用
文字だけのプレスリリースは、いくら内容が良くても読みづらいもの。適切な図表やグラフ、写真などの視覚的要素を加えることで、理解しやすさと印象が大きく変わります。
私が痛感したのは、ある製品発表のプレスリリースでした。最初は文章のみで配信したところ、ほぼ反応がなかったのに、同じ内容でも「製品の使用前後の比較写真」「効果を示すグラフ」「使用シーンのイメージ写真」を追加したバージョンを再配信したところ、5つのメディアから問い合わせがありました。
効果的な視覚的要素の例:
- データをグラフやチャートで表現(例:市場調査結果のグラフ)
- 製品やサービスの実際の写真(できればシーンがわかるもの)
- インフォグラフィックで仕組みやプロセスを説明
- 比較表で従来品や競合との違いを明示
ただし、あまりに多くの視覚素材を詰め込むと逆効果です。3つ程度に厳選し、それぞれに簡潔なキャプションをつけるのがポイントです。私も初めは「たくさん入れた方が良い」と勘違いして、10枚以上の写真を添付したことがありますが、「情報過多で何が重要かわからない」と指摘されたことがあります。
6. 人間的な要素・ストーリーの付加
数字やデータだけでなく、「人」にまつわるストーリーを含めることで、記者の心に響くプレスリリースになります。開発者のエピソードや、ユーザーの声、課題に取り組むきっかけとなった出来事など、感情に訴える要素が重要です。
あるヘルスケア製品のプレスリリースでは、当初は機能や効果だけを伝えていましたが、まったく反応がありませんでした。そこで「開発者自身の家族の健康問題がきっかけで開発に着手した経緯」や「実際に製品を使って改善した利用者の声」を盛り込んだバージョンに改訂したところ、健康雑誌やライフスタイル系メディアから大きな反響がありました。
効果的なストーリー要素:
- 開発の裏話やきっかけ(例:「創業者の実体験から生まれたアイデア」)
- 実際のユーザーの声や体験談(例:「使用後、△△さんの生活はこう変わった」)
- 開発過程での苦労や試行錯誤(例:「200回以上の試作を経て完成」)
- 企業理念や社会貢献への思い(例:「〇〇という社会課題に取り組む当社の決意」)
私の経験では、数字やスペックだけのプレスリリースより、「なぜ」「誰が」「どのような思いで」という要素を加えたプレスリリースの方が、記者からの問い合わせが2〜3倍多くなります。
7. 使いやすい追加素材の提供
記者が記事を書く際に役立つ追加素材を用意しておくことで、掲載率や掲載内容の質が向上します。具体的には、高解像度の写真や図版、詳細なデータシート、キーパーソンへのインタビュー内容などです。
私の失敗談の一つに、ある新製品発表のプレスリリースを配信した後、記者から「画像はありますか?」という問い合わせが複数あったことがあります。その時は慌てて用意しましたが、中には締め切りに間に合わず掲載を見送られたケースもありました。この経験から、事前に「記者が必要とする素材」を想定して準備することの重要性を学びました。
効果的な追加素材の例:
- 高解像度の製品・サービス画像(SNS用に正方形バージョンも)
- キーパーソンの顔写真(経営者や開発責任者など)
- 詳細なスペック表やデータシート
- 短いインタビュー動画やコメント集
- 企業ロゴや商品ロゴのクリアファイル
ある食品メーカーでは、プレスリリースとともに「手軽に使えるレシピカード」や「商品の魅力が伝わる調理シーン写真」を用意したところ、女性誌や料理メディアでの掲載率が大幅に向上したと聞いています。
追加素材はプレスリリースに直接添付すると重くなるため、ダウンロードリンクを記載したり、問い合わせに応じて提供できる旨を明記しておくのもよいでしょう。
記者の目を引く構成と表現テクニック
「記者の目を引く構成」と「記者が求める表現」を意識するだけで、プレスリリースの掲載率は格段に上がります。今回は、私の経験から導き出した、記者の心をつかむ構成と表現テクニックをご紹介します。
見出しとリード文の黄金法則
記者が一日に目を通すプレスリリースは、なんと50~100通にも上ります。そのため、最初の5秒で「これは書くに値する」と判断されなければ、残念ながらゴミ箱行きです。
私がかつて経験した失敗は、「企業視点の見出し」にこだわりすぎたこと。「〇〇社、新製品△△を発売」という定番の見出しでは、他社と差別化できないんですね。
そこで効果的なのが、以下の3つのパターンです:
- ニュース性の強調型:「業界初」「〇〇を実現する国内唯一のサービス」など
- 数字活用型:「作業時間を50%削減する〇〇をリリース」など
- 課題解決型:「増加する〇〇問題を解決する新サービス」など
私自身、ある健康食品メーカーのプレスリリースで「国内初、〇〇成分を配合した△△が糖質吸収を30%抑制」という見出しに変更したところ、それまで全く反応のなかった記者から3件も問い合わせがあったんです。目から鱗が落ちる思いでした。
リード文(最初の段落)も同様に重要です。ここでは5W1Hを意識しつつも、特に「なぜ今」「なぜあなたの会社が」「誰にとってどんなメリットがあるのか」をコンパクトに伝えましょう。長すぎるリード文は避け、150字程度に収めるのがベストです。
記者が求める5つの必須要素
何度もプレスリリースを出しても反応がなかった時期、実際に記者の方に「なぜ取り上げてもらえないのか」を直接聞く機会がありました。そこでわかったのは、記者が本当に求めているのは以下の5つの要素だったのです:
- 社会的背景や市場の課題:なぜその製品・サービスが必要なのか
- 明確な差別化ポイント:競合と比べて何が優れているのか
- 具体的なデータや数字:効果や実績を裏付ける客観的な情報
- ユーザーメリットの具体例:誰がどう使って何が改善されるのか
- 今後の展望:将来の計画や市場へのインパクト
特に「具体的なデータや数字」は欠かせません。「業界をリードする」「画期的な」といった抽象的な表現よりも、「〇〇比20%向上」「利用企業の△△が90%改善」などの具体的な数値の方が、記者にとって記事化しやすいのです。
私は以前、ある中小企業のプレスリリースを手がけた際、「導入企業の業務効率が向上」という表現を使っていました。しかし、実際のユーザー調査をもとに「導入企業の73%が残業時間を月平均15時間削減」と書き換えたところ、業界紙だけでなく一般紙にも取り上げられたんです。このときの喜びは今でも忘れられません。
NGワードと表現の言い換え例
プレスリリースを書いていると、つい使いたくなる言葉がありますよね。私も最初はよく使っていました。しかし、記者受けの悪い表現があることに気づいたんです。
例えば:
- ❌「革新的な」→ ⭕「〇〇の課題を△△の方法で解決する」
- ❌「業界トップクラス」→ ⭕「国内シェア〇〇%を誇る」
- ❌「多くのお客様に好評」→ ⭕「導入企業〇〇社のうち△△%が継続利用」
- ❌「使いやすい」→ ⭕「初めての操作でも平均△分で習得可能」
大手家電メーカーのプレスリリースを担当したとき、「使いやすさを追求した革新的デザイン」という表現を使っていました。これを「70代の高齢者モニター10名中8名が、説明書なしで5分以内に操作を完了できたデザイン」に変更したところ、高齢者向けメディアで大きく取り上げられたんです。いかに具体的な表現が重要かを身をもって経験しました。
また、記者が敬遠するフレーズとして「弊社代表〇〇は次のように述べています」に続く長い引用文があります。これは記者にとって使いづらい情報なのです。代わりに、短く要点をまとめたコメントを提供するほうが効果的です。
記者目線の構成テクニック
プレスリリースの構成にも、記者に配慮したポイントがあります。私がいつも心がけているのは「逆ピラミッド構造」。最も重要な情報を最初に持ってくる構成です。記者は忙しいので、最初の数行で「これは書く価値があるか」を判断します。
理想的な構成はこうです:
- 見出し・サブタイトル:核となるニュース価値を端的に
- リード文:5W1Hをコンパクトに
- 背景・課題:なぜ今このサービスが必要なのか
- 製品・サービスの概要:特徴と差別化ポイント
- 具体的なデータ:効果や実績を数字で
- 今後の展開:将来のビジョンや計画
- 会社概要:基本情報
また、自社の宣伝色が強すぎるとNGです。代わりに「市場課題の解決者」としての立場から情報を提供すると、記者に親切な印象を与えます。
私がこの構成を実践するようになったのは、とある記者から「この部分だけ切り取って使いやすいように書いてくれると助かる」というアドバイスをもらってからです。記者は本当に必要な情報を素早く見つけられるよう、情報の整理整頓が重要なんですね。
視覚的要素の効果的活用
文字情報だけでなく、視覚的要素の活用も掲載率アップの鍵です。以前は「文章さえしっかり書けば」と思っていた私ですが、ある記者から「画像が使えるとありがたい」と言われ、考えを改めました。
効果的な視覚素材には:
- 製品・サービスのビジュアル:高解像度の写真
- データの視覚化:グラフやチャート
- 使用シーンの画像:実際の利用状況
- インフォグラフィック:複雑な情報のビジュアル化
ただし、画像を添付する際は以下の点に注意しましょう:
- 画像サイズは大きすぎず小さすぎない(推奨:横幅1000px程度)
- ファイル形式はjpgやpngが望ましい
- 必ず「無断転載可」の旨を明記する
- 画像に関する簡潔な説明文(キャプション)を用意する
一度、新サービスのプレスリリースで「文章のみ」と「図解入り」の2パターンを用意して配信実験をしたところ、図解入りのバージョンが約2倍の掲載数を獲得しました。このときの経験から、私はどんなプレスリリースでも最低1つは視覚素材を添付するようにしています。
専門性と読みやすさのバランス
プレスリリースにおける難しいポイントの一つが、専門性と読みやすさのバランスです。特に技術的な内容のプレスリリースでは、この点に苦労することがよくあります。
ITベンチャーのプレスリリースを担当したとき、技術者から提供された文章が専門用語だらけで、正直なところ私自身も理解できないものでした。
そこで採用したのが「階層的な情報提供」です:
- 一般向け説明:高校生でも理解できるレベルの簡潔な説明
- 業界関係者向け説明:中程度の専門性を持つ詳細情報
- 専門家向け補足資料:技術仕様などの詳細情報(別資料として提供)
実践してみると、一般メディアと専門メディアの両方から取り上げられる機会が増えました。「これなら自分の読者にも説明できる」と記者に思ってもらえることが重要なんですね。
私自身、専門用語を理解するのに苦労した経験から、「自分の祖母に説明するとしたら」という視点でプレスリリースを見直すようにしています。これが意外と効果的なんです。
記者が心を動かされるストーリーの組み立て方
最後に、記者の心を動かすストーリー構成についてお話しします。ただ情報を羅列するのではなく、「なぜそのサービスが生まれたのか」という背景ストーリーが加わると、記事になりやすくなります。
あるスタートアップのプレスリリースでは、創業者自身の体験から生まれたサービスであることを強調しました。「自分の祖父が抱えていた〇〇という問題を解決するために開発した」という創業ストーリーを加えたところ、複数の生活情報メディアで大きく取り上げられたのです。
ストーリー構成の基本パターンとしては:
- 課題提起:社会や市場が抱える問題点
- 解決への道のり:その課題解決に向けた取り組み
- 克服と成果:どのような困難を乗り越え、何を実現したか
- 未来への展望:今後どのような社会的インパクトを目指すか
ただし、ストーリーに走りすぎて情報不足にならないよう注意が必要です。感動的なストーリーよりも、記者が記事にしやすい「事実とデータ」の提供を忘れないようにしましょう。
私の失敗談として、あるクライアントの感動的な創業ストーリーばかりに焦点を当てたプレスリリースを作成したことがあります。確かにストーリーは素晴らしかったのですが、「具体的に何をするサービスなのか」という基本情報が不足していたため、記者からの問い合わせが相次ぎました。バランスが大切なんですね。
効果的なプレスリリースを作成するには、記者の目線に立って「使いやすい情報」を提供することが何よりも大切です。派手さや美しい言葉遣いよりも、記者が記事化しやすい「具体性」と「明確さ」を心がけてみてください。きっとメディア掲載率が向上するはずです。
配信のタイミングと手法の最適化
プレスリリースの内容がどれだけ優れていても、配信のタイミングや手法が適切でなければ、せっかくの情報が記者の目に留まることはありません。私がPR業界で長年活動してきた中で、最も多く見てきた失敗パターンの一つが、この「配信のタイミングと手法の最適化」の欠如です。プレスリリース配信の最適なタイミングと手法についてお伝えします。
業界・メディア別の最適な配信タイミング
プレスリリースの配信タイミングは、想像以上に重要です。一般的には「火曜日から木曜日の午前中」がベストと言われていますが、実はそれほど単純ではありません。業界やターゲットメディアによって最適なタイミングは大きく異なります。
IT・テクノロジー系メディア
テクノロジー系メディアは、月曜日と金曜日を避けるのが鉄則です。月曜日は週末のニュースの消化で忙しく、金曜日は週末企画の準備で手一杯になっています。IT業界の場合、水曜日の午前10時~11時が最も開封率が高いというデータもあります。
私の経験では、火曜日の午前中がITメディアの反応が良いケースが多かったです。以前、あるソフトウェア企業のプレスリリースを火曜日午前10時に配信したところ、同日中に5つのテック系メディアから問い合わせがありました。対照的に、同じ企業の別のリリースを金曜日午後に配信した際は、ほぼ反応がありませんでした。
経済・ビジネス系メディア
経済メディアは、各社の決算発表スケジュールを把握しておくことが重要です。大手企業の決算発表日には避けるべきです。また、日銀の金融政策決定会合や重要経済指標の発表日も避けた方が無難です。
経済系の場合、水曜日の午前9時30分~10時30分がゴールデンタイムです。月曜朝はどの業界でも避けるべきですが、特に経済メディアは月曜朝の編集会議で一週間の方針を決めるため、その前に届いたプレスリリースは埋もれてしまいがちです。
生活・消費者向けメディア
生活情報や消費者向けの内容は、雑誌やウェブメディアのリードタイムを考慮する必要があります。多くの女性誌やライフスタイル系メディアは1~2ヶ月前に取材を終えるため、季節商品などはそれを見越した配信計画が必要です。
例えば、クリスマス商戦に関するプレスリリースは10月中旬までに配信すべきです。一度、クライアントのホリデーシーズン向け商品を11月下旬にリリースしたことがありましたが、「締め切りに間に合わない」とほとんどのライフスタイルメディアに言われてしまいました。しっかり逆算して計画すべきでした。
地方メディア向け
地方紙や地域メディアは、全国紙に比べて人員が少ないケースが多いです。そのため、午前9時~10時の早い時間帯に配信すると、その日の取材予定に組み込んでもらえる可能性が高まります。
地方メディア向けの配信では曜日よりも「地域の特性」を重視すべきです。地元の大きなイベントと重なる日は避け、逆に地域に関連性の高い内容であれば、その関連性を件名で明確にしましょう。
配信サービスの効果的な活用方法
プレスリリース配信サービスは、効率よく多くのメディアにリーチできる便利なツールです。しかし、闇雲に利用するだけでは効果は半減します。以下、主要サービスの特性と活用のポイントをご紹介します。
主要配信サービスの特性比較
- PR TIMES:国内最大級の配信サービスで、登録メディア数が多く、特にWeb系メディアとの相性が良いです。SEO効果も期待できますが、逆に言えば情報過多の状態でもあります。
- @Press:記者会見の実施サポートなど、付加サービスが充実しています。IT系や専門分野に強みがあります。
- ValuePress!:比較的リーズナブルな価格設定ながら、基本的な配信機能は充実しています。スタートアップや予算の限られた企業におすすめです。
- 共同通信PRワイヤー:全国の地方紙や専門紙への配信力が強みです。地域展開を重視する企業に向いています。
実は各サービスの配信先メディアには重複もありますが、得意分野が異なります。例えば、あるファッションブランドのクライアントでは、PR TIMESよりも@Pressの方が反応が良かったという事例もあります。業界によって相性の良いサービスを選ぶことが重要です。
効果を高めるための工夫
ワイヤーサービスで配信する際のポイントをいくつかご紹介します:
カテゴリ設定の最適化:多くの配信サービスでは、複数のカテゴリを選択できます。主カテゴリだけでなく、関連する副カテゴリもしっかり選んで、露出機会を増やしましょう。ただし、関係のないカテゴリを選びすぎると、印象が悪くなる可能性もあります。
タイトルの工夫:配信サービスでは特に件名が重要です。「【新商品】」「【調査結果】」などの接頭語を付けると、記者が内容を把握しやすくなります。また、数字を入れると開封率が20~30%向上するというデータもあります。
検索されやすいキーワードの配置:特にPR TIMESなどはSEO効果も期待できるため、検索されやすいキーワードをタイトルや冒頭に適切に配置することが重要です。ただし、不自然に詰め込むのは避けましょう。
添付資料の最適化:高解像度の画像やPDFは記者にとって使いやすい素材です。特に画像は、編集部で改めて撮影する手間を省けるため、掲載可能性が高まります。資料提供を明記した上で、プロのカメラマンが撮影した質の高い画像を用意することをおすすめします。
個別配信とワイヤーサービスの使い分け
私の経験では、最も効果的なのは「ワイヤーサービス」と「重要メディアへの個別配信」を組み合わせる方法です。
ハイブリッド配信の実践法
STEP1:ターゲットメディアのリスト化
まずは取り上げてほしい重要メディアを20社程度リストアップします。業界の主要メディア、ターゲット層が読むメディア、過去に掲載実績のあるメディアなどが候補です。
STEP2:個別配信の準備
リストアップしたメディアについては、担当記者の名前と連絡先を調査します。必要に応じて編集部に電話をかけ、適切な担当者を確認することも有効です。
STEP3:個別配信の実施
ワイヤーサービスでの配信の1時間前に、重要メディアには個別にメールを送ります。その際、件名に「本日○時にPR TIMESでも配信予定」と明記すると、記者は「急いで見るべき情報」と認識します。
STEP4:ワイヤーサービスでの配信
計画した時間にワイヤーサービスで一斉配信します。これにより、個別にアプローチしていないメディアにもリーチできます。
STEP5:フォローアップ
特に重要なメディアには、配信翌日に電話でフォローするのも効果的です。ただし、「掲載してください」と直接お願いするのではなく、「何か追加で必要な情報はありますか?」といった形で、サポートの姿勢を示すことが大切です。
実践事例:成功と失敗から学ぶ
あるベンチャー企業の新サービス発表では、このハイブリッド配信方式を採用しました。主要なテック系メディア15社には個別に配信し、その後PR TIMESでも公開しました。結果として、個別配信した15社中6社から反応があり、そのうち4社に掲載されました。さらにPR TIMES経由でも8社のメディアに掲載され、合計12社という高い掲載率を達成できました。
一方、失敗例としては、ある製造業のクライアントが新工場開設のニュースをワイヤーサービスのみで配信したケースがあります。地元メディアには個別アプローチすべきだったのですが、「ワイヤーサービスだけで十分」と判断してしまいました。結果、地元の重要紙には掲載されず、クライアントの期待を満たせませんでした。
タイミングを見極めるための業界カレンダー活用法
効果的な配信計画を立てるためには、業界のイベントカレンダーを作成し、活用することが重要です。
- 主要企業の決算発表スケジュール:特に自社と同業他社の決算発表日は避けるべきです
- 業界の主要展示会・イベント:展示会開催中はメディアの関心がそちらに向くため、重要なプレスリリースの配信は避けましょう
- 官公庁の統計発表日:経済指標や業界統計の発表日は経済ニュースが多くなるため注意が必要です
- 季節イベント前のリードタイム:クリスマス商戦なら10月中旬、夏商戦なら4月中旬といった具合に、季節商材は十分な余裕を持って配信しましょう
これらの情報を一つのカレンダーにまとめておくと、配信計画が立てやすくなります。私も数年前からこの方法を採用していますが、メディア掲載率が明らかに向上しました。
最後に強調したいのは、プレスリリースの配信は「数」ではなく「質」と「タイミング」が決め手だということです。年間100本配信するよりも、内容と配信方法を厳選した20本の方が、はるかに高い効果を生み出します。
何よりも大切なのは、記者の立場に立って考えることです。彼らが必要としている情報を、必要なタイミングで、最も受け取りやすい方法で届けることができれば、プレスリリースの効果は飛躍的に高まります。
次のセクションでは、配信後のフォローアップと記者との関係構築について詳しく見ていきましょう。プレスリリースの効果を最大化するためには、配信後の対応も非常に重要なのです。
フォローアップと関係構築のテクニック
プレスリリース配信後、「あとは記者の反応を待つだけ」と思っていませんか?実はここからが本当の勝負なんです。私がPR業界で15年以上活動してきた経験から言えることですが、フォローアップの質と関係構築の深さが、メディア露出の成果を大きく左右します。
配信後のアプローチ方法と注意点
プレスリリースを配信した後、どのようにフォローアップすればよいのか、多くのPR担当者が悩むポイントだと思います。私も初めてプレスリリースを担当したときは、「しつこくないフォローアップって一体どうすれば?」と頭を抱えていました。
まず大切なのは、タイミングです。プレスリリース配信から1〜2営業日後が最適なフォローアップのタイミングと言われています。これは記者が情報を確認する時間を確保しつつ、まだ記事化の検討段階にある可能性が高い時期だからです。あまりに早すぎると「見る時間もないのに」と思われてしまいますし、遅すぎると既に他の案件に移っている可能性があります。
「でも電話するのは気が引ける…」という声もよく聞きます。確かに私も最初はドキドキしながら電話していました。しかし、記者との信頼関係を築くためには、電話でのフォローアップが効果的なケースが多いんです。メールは埋もれがちですが、電話は直接コミュニケーションが取れるメリットがあります。
ただし、電話する際は以下の点に注意しましょう:
- 記者の締切時間を避ける:多くの記者は午後の締切前が忙しいため、午前中や夕方の方が対応しやすい傾向があります
- 簡潔に要点を伝える:「先日送付したプレスリリースについて補足情報があれば」と切り出し、30秒程度で要点を伝えます
- 取材の可能性を探る:「もし興味があれば、担当者インタビューなども可能です」と付け加えると良いでしょう
私が以前、ある製品リリースのフォローアップで失敗したのは、記者に「これは掲載する予定はありますか?」と直球で聞いてしまったことです。記者からは「こちらで判断します」とピシャリと言われてしまいました。その後、先輩から「記者は掲載の有無を直接約束することはほとんどない」と教えてもらい、アプローチを変えました。
より効果的なのは、「何か追加情報が必要でしたら」「写真や図表などご用意できますが」といった、記者の仕事をサポートする姿勢でアプローチすることです。これにより、「この広報担当者は役に立つ」という印象を残せます。
記者との良好な関係を築くポイント
記者との関係構築は一朝一夕にはいきません。私も長年かけて少しずつ信頼関係を築いてきました。メディア露出を継続的に獲得するためには、長期的な視点での関係構築が鍵となります。
記者の仕事を理解することがまず第一歩です。記者は日々膨大な情報の中から「読者にとって価値ある情報」を選び、限られた時間で記事にしています。彼らのプレッシャーや締切の厳しさを理解した上で接することで、自然と信頼関係が生まれます。
私は以前、ある記者から「御社の広報は情報が整理されていて助かる」と言われたことがあります。なぜそう言われたのか考えたとき、私が心がけていたのは以下のポイントでした:
- 情報の整理と簡潔さ:必要な情報を簡潔にまとめ、図表や写真も用意しておく
- 迅速な対応:問い合わせには可能な限り当日中に返答する
- 余計なプッシュをしない:掲載を強くお願いするのではなく、判断材料を提供する姿勢を持つ
- 記者の専門領域を理解する:その記者がどんなテーマに関心を持っているかリサーチしておく
特に効果的だったのは、記者ごとの関心領域をデータベース化していたことです。例えば、AさんはITの中でもAI関連に強い関心があり、Bさんは人材育成に関するトピックに詳しい、といった情報を蓄積。それに合わせたアプローチをすることで、「この情報は確かに自分の記事に役立つ」と思ってもらえる確率が高まりました。
とはいえ、関係構築の道のりで失敗することもあります。以前、ある記者にメールで何度もフォローアップしたことがありました。返信がないので「見ていないのかな」と思い、何度も送ってしまったんです。後日その記者と別件で会った際に「あまりにもメールが多くて少し困った」と言われてしまいました。ドキッとしましたが、素直に謝罪し、以降は適切な頻度でのコミュニケーションを心がけました。
リリース内容の発展的な展開方法
プレスリリースの内容を一度きりで終わらせるのはもったいないことです。一つのリリースから複数のメディア露出チャンスを創出する「発展的展開」を考えましょう。
私が実践している方法は、**”一つの情報の多角的な切り口化”**です。例えば新サービスのリリースなら:
- 統計データ軸:「○○業界の△△%が抱える課題を解決」という切り口で業界メディアへ
- 経営者インタビュー軸:「創業の思いとサービス開発秘話」でビジネスメディアへ
- ユーザー事例軸:「導入企業がこう変わった」という実績ベースで専門メディアへ
- 社会貢献軸:社会課題解決の側面を強調して、ソーシャルメディアへ
この方法を使って、ある製品リリースでは当初の3倍のメディア露出を獲得できました。一つの情報でも、伝える相手によって価値ある切り口は変わるんです。
また、**”時間軸での展開”**も効果的です。例えば:
- 事前告知:開発中の段階で、テスト結果や開発者インタビューを提供
- 正式発表:本リリース時に全情報を公開
- 導入後フォロー:リリース1ヶ月後に初期成果や利用者の声を発信
- 半年後レポート:6ヶ月経過時点での成果とデータを共有
こうした時間軸での展開により、一度のリリースで終わらせず、継続的な露出を得ることができます。私自身、あるプロジェクトでこの手法を試したところ、半年間で延べ15回のメディア掲載につながった経験があります。
さらに、業界イベントや季節トレンドとの連動も忘れてはいけません。例えば年末年始なら「今年のトレンドと来年の展望」、GW前なら「休暇中に試したい新サービス」など、タイミングに合わせた切り口で再アプローチすることで、掲載確率が高まります。
私たちのチームでは、一つのプレスリリースに対して、最低でも3つの展開方法を考えることをルール化しています。この習慣により、単発の露出で終わらせず、波状的なメディア露出を実現できるようになりました。
フォローアップの成功事例
具体的な成功例を共有します。あるスタートアップ企業のAIツールリリース時、以下のステップでフォローアップを行いました:
- 配信2日後:主要IT・ビジネスメディア10社に電話でフォロー。「デモ画面を用意できます」と伝える
- 1週間後:反応があった3社に対し、CTOへのインタビュー機会を提案
- 2週間後:まだ反応のないメディアに、初期ユーザーの声をまとめたデータを送付
- 1ヶ月後:業界イベントでの発表情報と絡めて再アプローチ
結果として、最初のアプローチでは1社だけだった掲載が、最終的には7社のメディアで取り上げられました。特に効果的だったのは、初期ユーザーからの具体的なフィードバックデータでした。記者が「読者にとっての実用価値」を判断する材料となったのです。
別の事例では、記者との関係構築により、リリースしなかった小さな機能アップデートさえも記事化してもらえるようになったケースもあります。これは日頃から「この記者にはこんな情報が役立つかも」と考え、定期的に情報提供を続けてきた結果でした。
フォローアップと関係構築は、単なる「掲載のお願い」ではなく、「記者の仕事をサポートする姿勢」が何より大切です。記者が求める情報を、求めるタイミングで、使いやすい形で提供し続けることが、長期的な信頼関係構築の鍵となります。
失敗を恐れず、一つひとつの経験から学びながら、あなたらしいフォローアップスタイルを確立していってください。最初は難しく感じても、継続的な実践と改善により、必ず成果は現れます。記者との関係は、PR活動の中で最も価値ある資産になるはずです。
効果測定と継続的な改善
プレスリリースを配信したら終わり、ではありません。実は、ここからが本当の意味での「効果的な」プレスリリース活動の始まりなのです。20年以上PRに携わってきた私の経験から言うと、多くの企業がこの「効果測定と改善」のプロセスを軽視しがちです。でも、ここをしっかりと行うかどうかで、長期的なPR効果に大きな差が生まれるんですよ。
私が以前、ある中小企業のPRを担当したとき、最初の数回のプレスリリースはほとんどメディアに取り上げられませんでした。正直なところ、かなり落ち込みました。でも、そこであきらめずに各リリースの反応を細かく分析し、徐々に改善を重ねていったんです。その結果、半年後には掲載率が3倍以上に向上し、業界紙だけでなく全国紙にも取り上げられるようになりました。
具体的なKPIの設定方法
効果測定の第一歩は、明確なKPI(重要業績評価指標)を設定することです。「メディアに掲載されればOK」という漠然とした目標ではなく、具体的な数値目標を持つことが重要です。
私がお勧めするプレスリリースのKPI設定は以下のようなものです:
- 掲載数:単純な掲載メディア数(例:10媒体以上の掲載を目指す)
- 掲載メディアの質:ターゲット層が接触する主要メディアでの掲載率(例:ターゲットメディア5媒体中3媒体での掲載)
- 内容の質:単なる事実の羅列ではなく、企業メッセージが正確に伝わっているか(例:企業の主要メッセージが70%以上含まれた形での掲載)
- 二次利用率:SNSでのシェア数やオーガニック検索からの流入増加
- 問い合わせ増加率:プレスリリース配信後の問い合わせ数の変化
最初は全部を一度に測定するのは大変かもしれません。まずは「掲載数」と「掲載メディアの質」という比較的測定しやすい指標から始めて、徐々に測定範囲を広げていくのがおすすめです。
「でも、どうやって目標値を決めればいいの?」と思われるかもしれません。これは業界や企業規模によって大きく異なりますが、最初は自社の過去のデータを基準にするのが良いでしょう。例えば、「前回よりも掲載数20%増」といった具合です。もし過去データがなければ、業界平均や競合他社の状況を参考にしてみてください。
データに基づく効果分析の手法
KPIを設定したら、次は実際にデータを集める段階です。ここでやりがちな失敗は、「感覚」や「印象」に頼った評価をしてしまうこと。「なんとなく良かった」ではなく、数字で語れるようにしましょう。
効果測定に使える主なツールやテクニックをご紹介します:
- クリッピングサービス:専門のクリッピングサービスを利用して、メディア掲載を漏れなく把握する
- Google Analytics:自社サイトへの流入分析(プレスリリース配信日前後の比較)
- SNS分析ツール:Twitter、Facebook等での言及・シェア数の測定
- メディアモニタリングツール:Meltwater、Cisionなどのツールで包括的な分析
私自身、以前はエクセルで地道に記録していましたが、今はツールを活用することで分析の精度と効率が格段に上がりました。特にGoogleアラートの設定は無料でできる基本的な対策として必須です。自社名やキーワードでアラートを設定しておくと、新しい掲載があったときに通知が来るので見逃しが減ります。
データを収集したら、次は「なぜ」を考えることが重要です。「なぜこのメディアには掲載されなかったのか」「なぜこの記事は大きく取り上げられたのか」という分析をしていきましょう。
例えば、あるクライアントの事例では、データ分析の結果、「数字を含むタイトルのプレスリリースは掲載率が2倍高い」という傾向が見えてきました。また、「火曜日配信の方が月曜日配信よりも30%掲載率が高い」といった発見もありました。こうした小さな気づきの積み重ねが、次第に大きな成果につながるのです。
PDCAサイクルを活用した改善プロセス
効果的なプレスリリース戦略は、一回で完成するものではありません。継続的な改善のサイクル、いわゆるPDCA(Plan-Do-Check-Action)を回していくことが大切です。
私が実践している具体的なPDCAの回し方をご紹介します:
- Plan(計画):
- 目標とするKPIの設定
- ターゲットメディアのリスト化
- リリース内容と配信タイミングの計画
- Do(実行):
- プレスリリースの作成・配信
- 記者へのフォローアップ
- 必要に応じた追加情報の提供
- Check(評価):
- 設定したKPIに対する結果測定
- メディア別の反応分析
- 記者からのフィードバック収集
- Action(改善):
- 成功/失敗要因の特定
- 次回のリリースへの改善点リスト作成
- 記者との関係性強化のための施策検討
この一連のサイクルを3~4回ほど回すと、自社のプレスリリースの「効くパターン」が見えてくるものです。例えば「うちの会社は事例を具体的に書くと掲載されやすい」とか「業界データと組み合わせると価値が高まる」といった法則性が分かってきます。
実際に私がIT企業のPRを担当していたときは、最初はテクニカルな内容を前面に出していたのですが、あまり反応がよくありませんでした。そこでPDCAを回す中で、「エンドユーザーのメリットを冒頭に持ってくる」という改善を行ったところ、掲載率が2倍に跳ね上がりました。ちょっとした変更でも、効果は大きく変わるものなんですよ。
成功パターンの蓄積と標準化
効果測定と改善を続けていくと、自社にとっての「成功パターン」が見えてきます。これを社内で共有し、標準化することで、担当者が変わっても一定の効果を上げられるようになります。
成功パターンを蓄積するためのポイントとして、以下の3つが重要です:
- 成功事例のデータベース化:
良い反応を得たプレスリリースとその特徴を記録・整理する - テンプレート化:
効果の高かった構成やフレーズをテンプレート化して再利用しやすくする - チェックリスト作成:
「効くプレスリリース」の要素をチェックリスト化する
私の経験では、このような「型」を作っておくことで、忙しい時期でも効果的なプレスリリースを安定して作成することができるようになります。ただし、型に頼りすぎて創意工夫を忘れないよう注意することも大切です。パターン化しつつも、常に新しい切り口を模索する姿勢を持ち続けましょう。
最後に、効果測定と改善のプロセスで最も重要なのは「継続性」です。一度や二度の計測では傾向は見えてきません。最低でも半年程度、できれば1年以上継続して測定・改善を続けることで、確かな成果につながる知見が得られるでしょう。
「面倒くさい」と思うこともあるかもしれませんが、この地道な作業こそが、プレスリリースの効果を最大化する王道なのです。焦らず、着実に、そして継続的に改善を重ねていきましょう。そうすれば、予算をかけずとも、徐々にメディア露出は増えていくはずです。
さいごに
プレスリリースの効果を最大化するというのは、決して難しい技術ではありません。長年PRの現場で様々なプレスリリースを見てきた経験から言えることは、記者に「取り上げたい」と思わせる情報発信には明確なパターンがあるということです。
最も重要なのは、記者の立場に立って考えることです。日々大量のプレスリリースが記者のもとに届く中、彼らはどのような基準で選別しているのでしょうか。実は記者は「読者にとって価値ある情報か」「なぜ今これを伝える必要があるのか」という視点で常に判断しています。
私が初めて大規模なプロダクトローンチのプレスリリースを担当したとき、社内では「画期的な機能」と絶賛されていた内容を、そのまま記載して配信しました。結果は散々。メディア掲載はわずか2社だけでした。原因を探るために勇気を出して記者に直接連絡したところ、「御社にとっては画期的でも、読者にとってのメリットが伝わってこない」とストレートな指摘を受けました。
この失敗から学んだのは、「自社視点」ではなく「読者視点」でプレスリリースを構成することの重要性です。改めて読者にとっての具体的なメリットを数値化し、業界全体の課題解決につながる側面を強調したリライトバージョンを配信したところ、10社以上の掲載につながりました。
また、プレスリリース活動は単発で終わらせるものではなく、継続的なメディアとの関係構築という側面も持っています。あるクライアントの例では、最初は注目されなかったものの、定期的な情報提供と丁寧なフォローアップを続けることで、徐々に記者との信頼関係が築かれ、半年後には些細な新機能のアップデートでさえ取り上げてもらえるようになりました。
この記事で紹介した「記者の心をつかむ構成」「配信のタイミングの最適化」「フォローアップの重要性」などのテクニックは、すぐに実践できるものばかりです。一朝一夕で劇的な結果が出るわけではありませんが、地道に積み重ねることで確実にメディア掲載率は向上します。
最後に強調したいのは「評価と改善のサイクル」の重要性です。プレスリリース活動も他のマーケティング活動と同様、PDCAサイクルを回すことで継続的に効果を高められます。掲載された記事と掲載されなかった内容を比較分析し、自社のプレスリリースの強みと弱みを把握することで、次回の配信はさらに効果的になるはずです。
明日からでも実践できるこれらのテクニックを活用して、メディアと良好な関係を構築しながら、効果的な情報発信を実現してください。プレスリリースは単なる情報発信の手段ではなく、企業とメディア、そして読者をつなぐ重要なコミュニケーションツールなのです。
PR活動の成功は一朝一夕では実現しませんが、この記事で紹介したアプローチを地道に実践することで、必ず成果は表れます。小さな一歩から始めて、貴社のストーリーを世界に伝えていきましょう。