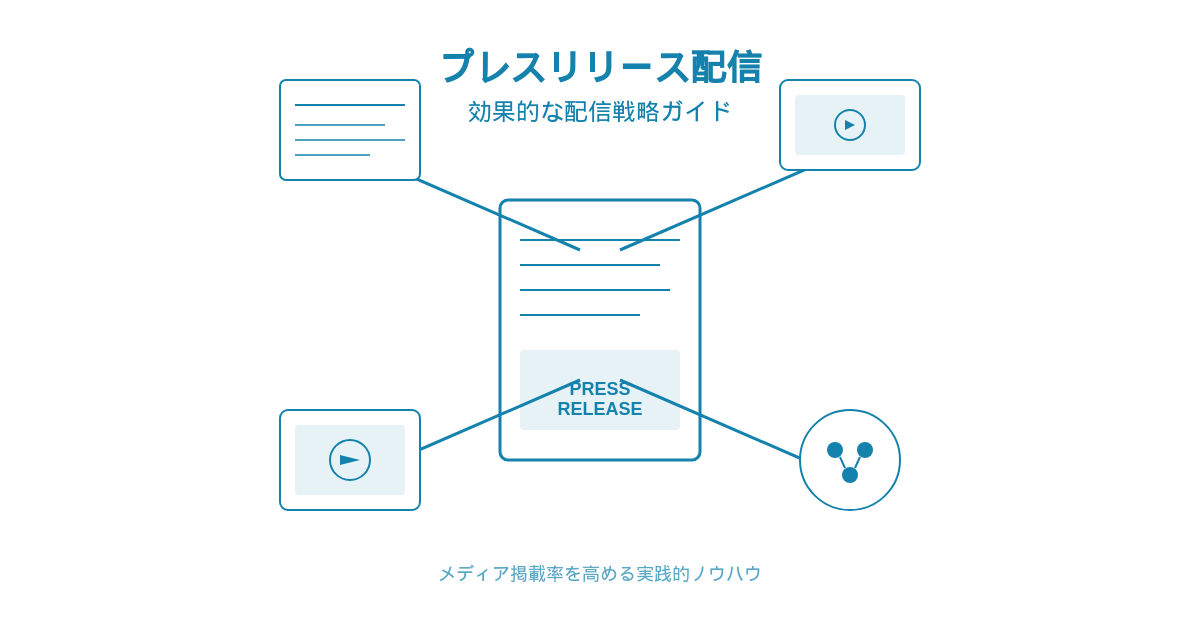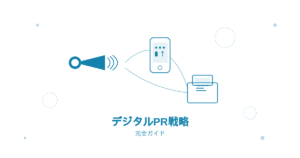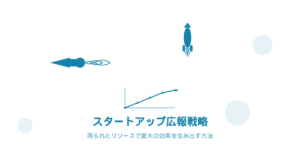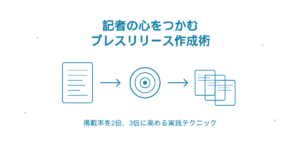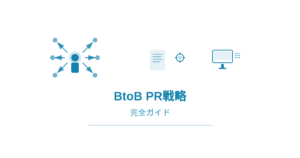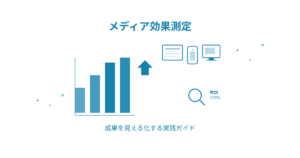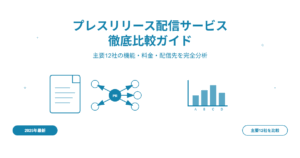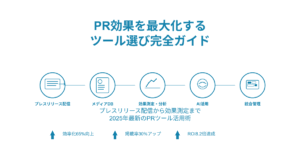プレスリリースは企業の重要なコミュニケーションツールであり、その配信方法一つで成果が大きく変わってきます。私が広報担当になりたての頃、「どのタイミングで配信すれば効果的なのか」「配信後はどうフォローすればいいのか」と頭を抱えた経験があります。思い返せば、最初のプレスリリース配信は大失敗でした。配信時間を誤り、ほとんどのメディアの締め切り後に送ってしまったのです。メディア掲載はゼロ。その日の帰り道は本当に落ち込みました。
その後、試行錯誤を重ね、数百件のプレスリリース配信を経験する中で、効果的な配信のノウハウを蓄積してきました。配信サービスの特性を理解し、メディアごとの締め切り時間を把握し、記者との関係構築を進めることで、プレスリリースの掲載率は着実に向上していきました。
本記事では、プレスリリース配信における「知っておくべき基礎知識」から「効果を最大化するテクニック」まで、実践ベースで解説します。メディア掲載率を高め、企業の認知度向上やブランディングに貢献するプレスリリース配信のコツをマスターしましょう。これから学ぶノウハウを実践すれば、あなたのプレスリリースがメディアに取り上げられる確率は格段に上がるはずです。
その他プレスリリース関連の記事もあわせてご確認ください。
➡️ 関連記事:プレスリリースを効果的に書くための7つの要素|メディア掲載率3倍の実践テク
➡️ 関連記事:【保存版】プレスリリース配信サービス比較12社|失敗しない選び方とコスト分析
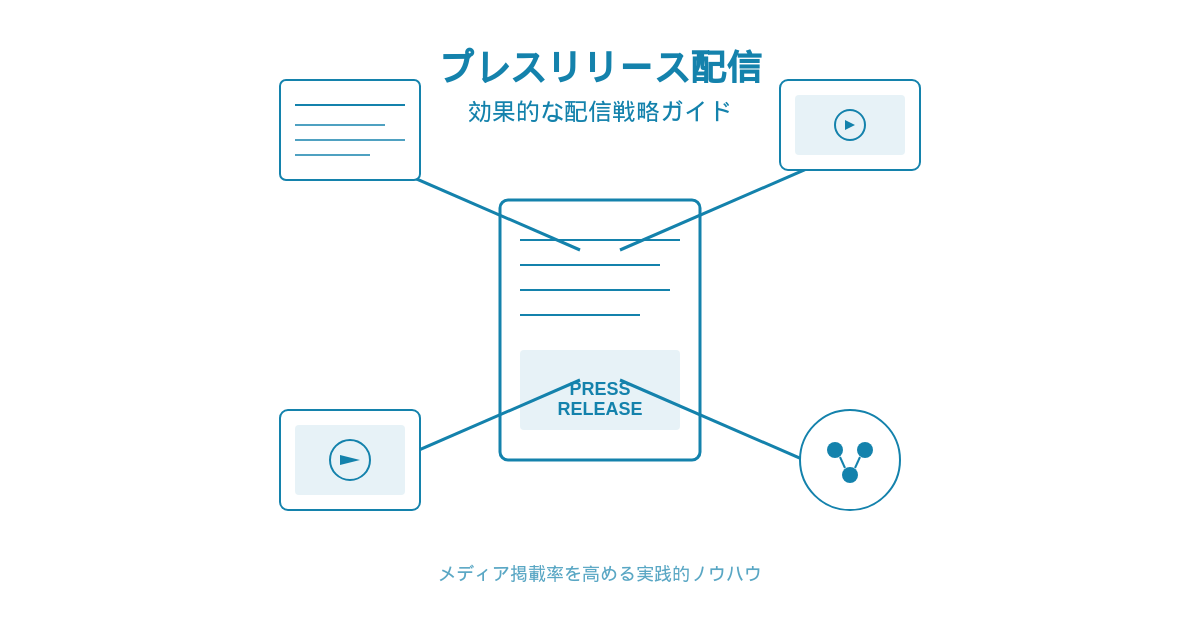
プレスリリース配信の基本と重要性
プレスリリース配信は、ただ情報を送り出せばいいというものではありません。私が初めて大規模な製品発表会のプレスリリースを担当したとき、「良い内容さえあれば勝手に記事になる」と甘く考えていました。しかし、実際にはいくら素晴らしい内容でも、配信のタイミングや方法を誤ると、まったく反響がないということが起こり得るのです。
ニュース価値の見極め方
プレスリリースを配信する前に、まず自社の情報に本当にニュース価値があるのかを冷静に評価する必要があります。私の経験では、「自社にとって重要」と「メディアにとってニュース価値がある」は別物だということ。ある時、社内では大盛り上がりだった小さな機能アップデートのプレスリリースを配信しましたが、ほとんど反応がありませんでした。
ニュース価値を見極めるポイントは以下です:
- 市場への影響度(業界初、市場規模など)
- 社会的意義(社会課題解決、SDGsへの貢献など)
- 数字の具体性(売上〇〇%増、利用者〇〇人突破など)
- 著名人や大手企業との協業
特に数字は重要です。「売上が好調」より「前年比120%の売上成長」のほうが具体的で、記者の目に留まりやすくなります。
配信タイミングの重要性
プレスリリース配信のタイミングは、掲載率を左右する決定的な要素です。私が痛感したのは、記者の仕事の流れを理解することの大切さ。各メディアには締め切り時間があり、それを過ぎると翌日以降の掲載になってしまいます。
一般的な目安としては:
- 朝刊メディア向け:前日15時までに配信
- 夕刊メディア向け:当日9時までに配信
- Webメディア向け:10時〜14時の間に配信
また、曜日選びも重要です。月曜日は週明けで記者も忙しく、金曜日は週末企画が多いため、火曜日から木曜日の配信が効果的なケースが多いです。ただし、記者の忙しさは時期によっても変わります。決算発表シーズンや大型イベント時期は避けるなど、業界カレンダーを把握しておくといいでしょう。
私が最も反省しているのは、ある新サービス発表のプレスリリースを大手企業の決算発表日に配信してしまった失敗です。記者の目に留まることなく埋もれてしまいました。事前にメディアカレンダーをチェックしておけば防げたミスでした。
社内承認フローの最適化
プレスリリースは対外的な公式発表ですから、社内で適切な承認を得ることが不可欠です。しかし、あまりに複雑な承認フローは配信タイミングを逃す原因になります。
私のチームでは以下のような承認フローを構築しました:
- 担当部署による事実確認
- 法務部によるリーガルチェック
- 広報責任者の最終確認
このフローを明確にし、各ステップの所要時間の目安も設定しておくと、配信日から逆算してスケジュールを組めます。一度、重要なプレスリリースが法務チェックで大幅修正となり、予定していた配信日に間に合わなかった経験から学びました。今では、重要度の高いリリースは法務チェックに3営業日、通常のリリースは2営業日と余裕をもって計画しています。
メディア特性の理解
各メディアには特性があり、それを理解することで効果的な配信が可能になります。業界専門誌は詳細な技術情報を求める一方、一般紙はより社会的意義やインパクトを重視します。Webメディアは速報性を重視し、ビジュアル素材が充実していると取り上げられやすい傾向があります。
私が担当したあるB2B製品のプレスリリースでは、専門メディア向けには技術仕様書を追加資料として用意し、一般メディア向けには市場規模や社会的インパクトを強調したサマリーを別途作成しました。結果、専門誌では詳細な製品レビュー記事に、一般紙ではビジネストレンドの一例として取り上げられるという、異なる形での露出を獲得できました。
メディアごとの特性をデータベース化し、プレスリリースの内容に応じて最適なメディアを選択できるようにしておくと効率的です。長年の経験から、「このテーマならこのメディアが反応しやすい」という感覚も養われていきます。
プレスリリース配信は、単なる情報発信ではなく戦略的なコミュニケーション活動です。適切なタイミングで、適切なメディアに、適切な内容を届けることで、その効果は何倍にも高まります。基本を押さえた上で、次のセクションで紹介する配信方法の選択に進みましょう。
➡️ 関連記事:「失敗しないPR戦略立案ガイド:効果測定からPDCAまで徹底解説」では、より戦略的な視点でのプレスリリース活用方法について詳しく解説しています。
プレスリリース配信の基本と重要性
ある企業が発表した新製品のプレスリリースが一切メディアに取り上げられなかった経験、私も痛いほど覚えています。「内容はバッチリなのに…」と落胆したものの、後から気づいたのは配信のタイミングと方法に大きな問題があったということ。このような失敗経験から学んだプレスリリース配信の基本と重要性についてお伝えします。
プレスリリース配信とは単に「情報を送る」だけの行為ではありません。企業の重要なニュースを最適なタイミングで、最適なメディアに届けることで、ビジネス成果に直結する戦略的コミュニケーション活動なのです。効果的な配信によって、企業認知度の向上、商品・サービスの販促効果、さらには企業価値の向上まで期待できるんですよ。
配信のタイミングとニュース価値の見極め方
「いつ配信すれば記事化されやすいのか」という質問をよく受けます。結論からいうと、一般的には火曜日から木曜日の午前10時から午後2時が最適とされています。特に午前10時台の配信は、記者が一日の取材計画を立てる時間帯と重なるため、検討される可能性が高まります。
ただし、業界によって最適なタイミングは異なります。例えば、金融関連なら市場が閉まった夕方以降、ITやテック関連なら午前中が効果的なケースが多いです。また、大きなニュースが予定されている日(決算発表日や国の重要発表など)は避けるなど、競合情報にも目を配る必要があります。
私の失敗体験からのアドバイスとしては、「火曜午前配信」を基本としつつも、自社の過去データを分析し、最も掲載率が高かったタイミングを把握することをおすすめします。データがなければ、小規模なリリースから開始して、タイミングの検証を始めてみるのも良いでしょう。
配信前の社内承認フローと確認ポイント
プレスリリースを配信する際の最大のリスクの一つが「誤情報の配信」です。一度配信したプレスリリースを修正するのは非常に難しく、修正配信自体がネガティブな印象を与える可能性もあります。
私が以前担当したプロジェクトでは、製品スペックの記載ミスにより、お客様に大きな誤解を与えてしまったことがありました。この経験から学んだのは、配信前の徹底したチェック体制の重要性です。
実践的な承認フローとして効果的なのは以下の手順です:
- 担当部署による事実確認
- 法務部門によるリスクチェック
- 経営層による最終承認
- 配信直前の最終確認(誤字脱字、リンク先、日付など)
特に気をつけたいのが「数字」と「日付」です。発売日や価格、性能などの数値は二重三重にチェックしましょう。また、アクセスURLや問い合わせ先の電話番号なども必ず動作確認をしてください。配信直前に「最終チェックリスト」を用意しておくと、慌ただしい状況でも確認漏れを防げますよ。
メディアごとの特性理解と配信方法の選択
かつて私は「同じプレスリリースを全メディアに一斉送信すれば効率的だ」と考えていました。しかし、この方法が逆効果になったケースを何度も経験し、メディアごとの特性理解の重要性を痛感しました。
例えば、専門メディアには技術的な詳細情報が求められますが、一般メディアには「なぜそれが一般の人にとって重要なのか」という視点が必要です。配信方法を選ぶ際には、まず「誰に何を伝えたいのか」を明確にすることから始めましょう。
メディアごとの特性を理解するためには、普段からそのメディアに目を通し、どのような切り口の記事が多いかを観察することが大切です。「この記者はこういう視点で記事を書く傾向がある」といった情報をストックしておくと、配信時に役立ちます。
また、記者との関係構築も非常に重要です。私は年に数回、担当記者と情報交換の場を設けていますが、こうした関係があると、プレスリリース配信後のフォローアップがスムーズになります。まずは業界の主要メディア2~3社からコンタクトを始めてみるといいでしょう。
➡️ 関連記事:【2025年版】記者関係構築ガイド:PR担当者のための実践戦略
効果的な配信のためのチェックリスト
長年のPR経験から作成した、配信前の最終チェックリストをご紹介します:
- 配信日時は最適か(競合イベント、市場の状況を確認)
- 全ての情報が事実確認済みか
- 数字、日付、料金などの重要情報に誤りはないか
- 問い合わせ先の情報(電話番号、メール)は正確か
- 画像・添付資料のリンクは正常に機能するか
- 経営層を含む関係者全員の承認を得ているか
- エンバーゴ(情報解禁日時)の指定は明確か
- 配信後の問い合わせ対応者は確保できているか
このチェックリストを使うことで、配信前の不安を大幅に減らすことができます。特に初めてプレスリリースを担当する方は、このリストを印刷して手元に置いておくことをおすすめします。
配信後の即時対応準備
プレスリリースを配信した後は「待ち」の状態になると思いがちですが、実はここからが勝負です。配信直後から24時間は記者からの問い合わせが集中しやすい時間帯です。
私が経験した例では、ある新製品のプレスリリース配信後、想定以上の反響があり、問い合わせ対応が追いつかなかったことがありました。結果として、いくつかの重要なメディアへの対応が遅れ、記事化の機会を逃してしまったのです。
この教訓から、配信後の対応チームを事前に編成し、質問が予想される内容とその回答集を準備しておくようにしています。また、担当者が不在の場合の代理対応者も決めておくと安心です。
プレスリリース配信は「する」ことがゴールではなく、「メディアに取り上げられること」「読者に届くこと」がゴールです。そのためには、配信の準備段階から配信後のフォローまで、戦略的に取り組むことが重要なんですね。
特にデジタル化が進む現代では、オンラインニュースの速報性を意識した配信計画が必要です。SNSとの連携も視野に入れ、プレスリリース配信後すぐにソーシャルメディアでも情報発信できる準備をしておくと、より広範囲に情報を届けることができますよ。
プレスリリース配信の基本を押さえ、重要性を理解することで、企業の情報発信力は格段に向上します。次のセクションでは、より具体的な配信方法の比較と選択について解説していきます。まずは自社の状況と目的に合わせた基本的な配信戦略を整えてみてくださいね。
主要なプレスリリース配信方法の比較
プレスリリース配信の方法は多岐にわたり、それぞれに特徴があります。私自身、PR会社で10年間様々な企業のプレスリリース配信を担当してきた経験から言えることは、「配信方法の選択一つで結果が大きく変わる」ということです。ここでは主要な配信方法を比較し、それぞれのメリット・デメリットを徹底解説します。
配信サービス(一斉配信)の活用
私が初めてPR担当になったとき、最も悩んだのは「どうやってメディアにリリースを届けるか」という点でした。そんなとき、上司に紹介されたのが配信サービスでした。
配信サービスとは、PR Times、ValuePress、@Pressなどの企業が提供するサービスで、一度の操作で多数のメディアにプレスリリースを配信できるプラットフォームです。最近では月額1万円台から利用できるサービスも増え、中小企業でも手が届きやすくなっています。
メリット
- 一度の操作で数百~数千のメディアに同時配信できる
- 24時間いつでも配信可能
- 掲載結果の自動レポート機能で効果測定が簡単
- サービス自体がニュースサイト化しており、そこからの露出も期待できる
デメリット
- 費用がかかる(月額1万円~10万円程度、プランによる)
- 配信数が多い分、個別メディアへの配慮が難しい
- 他社のリリースと同列に並ぶため埋もれやすい
私の経験では、新商品発表や企業の基本的なニュースは、こうした配信サービスが非常に効率的です。ある化粧品メーカーのクライアントでは、個別配信だけでは月に2~3件の掲載だったものが、PR Timesを併用することで平均10件以上の掲載を獲得できるようになりました。ただし、「配信すれば終わり」と考えるのは大きな間違いです。後述するフォローアップがさらに重要になってきます。
メディアへの個別配信のポイント
配信サービスが便利だからといって、個別配信の価値が下がったわけではありません。むしろ、情報過多の時代だからこそ、ターゲットを絞った丁寧な個別配信の重要性は高まっています。
以前、ある製造業のクライアントで、業界専門誌への掲載を目指していた時のことです。初めは配信サービスだけを使っていましたが、まったく結果が出ませんでした。そこで、専門誌の記者に個別にアプローチすることにしたのです。
個別配信のメリット
- 記者との関係構築につながる
- 記事内容のカスタマイズが可能(メディアごとの切り口提案)
- 専門性の高いニッチなメディアへのアプローチに最適
- フォローアップがしやすい
デメリット
- 時間と労力がかかる
- メディアリストの作成・更新が必要
- 記者の異動・退職への対応が必要
- 記者の好みやメディアの方針を把握する必要がある
個別配信で最も重要なのは「記者の目線」に立つことです。私は何度も失敗を重ねながら、以下のポイントが効果的だと学びました:
- メールの件名は勝負どころ:「プレスリリース」という言葉だけでなく、核となるニュース価値を簡潔に入れる
- 本文冒頭で要点を明確に:記者は忙しいので、最初の3行で興味を引けなければ読まれない
- 取材アレンジの提案:必要に応じて「取材可能です」と明記する
- 送信タイミング:朝9時~10時、または夕方16時~17時が読まれやすい(朝のニュース会議前、夕方の整理時間)
ある食品メーカーのケースでは、同じリリース内容でも、一斉配信と個別配信を使い分けることで、一般消費者向けのウェブニュースと、業界専門誌の両方での露出を獲得できました。効果を最大化するには、両方のアプローチを組み合わせるのが理想的です。
オウンドメディアでの公開と活用術
最近では、自社サイトやブログでプレスリリースを公開する「オウンドメディア配信」の重要性も高まっています。私自身、この方法を軽視していた時期がありましたが、あるデジタルマーケティング会社との仕事を通じて、その価値を実感しました。
オウンドメディア配信のメリット
- 配信コストがほぼゼロ
- 自社のSEO強化につながる
- ソーシャルメディアでの拡散に活用できる
- 掲載期間や内容の制限がない
- 自社サイトへのトラフィック増加
デメリット
- メディアへの直接配信にはならない
- 自社サイトの訪問者数に依存する
- 信頼性がメディア掲載より低く見られることがある
効果的なオウンドメディア活用のポイントは、「単なるリリース転載」から一歩進むことです。例えば、あるITサービス企業では、プレスリリースの基本情報に加えて、以下のような工夫を取り入れていました:
- 開発担当者のコメントを追加:メディア向けリリースよりも詳細な背景情報を提供
- 関連資料のダウンロード提供:ホワイトペーパーなど補足資料を用意
- デモ動画の埋め込み:文字だけでは伝わりにくい機能を視覚的に説明
- 過去の関連記事へのリンク:自社の関連コンテンツへの誘導
私が担当したベンチャー企業のケースでは、プレスリリースをオウンドメディアに掲載し、それをSNSで拡散することで、配信サービスを使わなくても業界メディアからの問い合わせにつながりました。特に専門性の高い内容や、ファンが多い企業の場合、この方法は非常に効果的です。
ソーシャルメディアを活用した配信手法
プレスリリースというと従来型のメディア向け配信をイメージしがちですが、最近ではソーシャルメディアを活用した配信も重要な選択肢になっています。実は私も最初は懐疑的でしたが、あるアパレルブランドとの仕事で、その効果に驚かされました。
ソーシャルメディア活用のメリット
- ターゲット層に直接アプローチできる
- 即時性が高く、リアルタイムの反応が見られる
- 視覚的要素(画像・動画)を効果的に使える
- 拡散性があり、バイラル効果が期待できる
- メディア記者も情報収集に利用している
デメリット
- 他の投稿に埋もれるリスクがある
- プラットフォームごとに最適化が必要
- 炎上リスクがある
- 企業アカウントのフォロワー数に依存する
効果的なソーシャルメディア配信のコツは、「プレスリリースの丸投げ」ではなく、各プラットフォームの特性に合わせた発信です。例えば:
- Twitter: 要点を140字に凝縮し、詳細はリンク先へ誘導
- Instagram: ビジュアルインパクトを重視したクリエイティブでストーリー性を持たせる
- LinkedIn: B2Bビジネスや人事関連の専門的な内容に適している
- YouTube: 商品デモや記者発表会のライブ配信などに活用
あるテック企業の新サービス発表では、プレスリリースをTwitterで先行公開し、専門メディアの記者が自発的に取り上げるという展開がありました。この方法は特に「今すぐ伝えたい」緊急性の高いニュースや、ビジュアルで訴求力が高まる商品・サービスに効果的です。
配信方法の選択基準とは
これまで様々な配信方法を紹介してきましたが、「どの方法を選ぶべきか」というのが最も重要な問いです。私の10年の経験から言えることは、以下の要素で判断するのが最も効果的だということです:
- ニュースの性質: 業界関係者向けの専門的な内容か、一般消費者にも関心を持たれる内容か
- 予算と人的リソース: 配信サービスの費用や担当者の時間的余裕
- 配信の緊急性: すぐに広く伝えたいのか、じっくり浸透させたいのか
- ターゲットメディア: 専門メディア狙いか、一般メディア狙いか
- 過去の実績: 同様のニュースでどの配信方法が効果的だったか
例えば、ある中小企業のクライアントでは、限られた予算の中で最大限の効果を出すために、次のような組み合わせが効果的でした:
- 重要な新商品発表 → 配信サービス + 重要メディアへの個別配信
- 小規模なアップデート → オウンドメディア + ソーシャルメディア
- 業界向け技術情報 → 専門メディアへの個別配信 + LinkedIn
失敗から学んだ最大の教訓は、「一つの配信方法に頼らないこと」です。かつて私は配信サービスだけに頼って大切なリリースを配信し、ほとんど成果が出なかった苦い経験があります。それ以降は、複数の配信チャネルを組み合わせる「マルチチャネル配信」を基本としています。
最後に、どの配信方法を選ぶにしても、「記者や読者にとって価値のある情報は何か」という視点を忘れないことが重要です。配信方法以前に、内容自体の価値が低ければ、どんなに優れた配信テクニックを用いても効果は限定的です。私も何度も失敗と成功を繰り返しながら、この原則に立ち返ることの大切さを実感しています。
➡️ 関連記事:「[プレスリリース配信サービス 比較]各サービスの特徴と選び方」へリンク
配信先メディアの選定とアプローチ
プレスリリースを配信する際、「誰に届けるか」という視点はとても重要です。私がPR担当として10年以上働いてきた経験から言えば、闇雲に多くのメディアに配信するよりも、戦略的に配信先を選定する方が効果的です。ここでは、メディア選定の考え方からアプローチ方法まで詳しく解説します。
ターゲット層に応じたメディア選定の基準
プレスリリースを配信する際、最初に明確にすべきなのは「誰に届けたいのか」ということです。私が初めてプレスリリースを担当したとき、とにかく多くのメディアに配信すれば効果が上がると思っていました。結果は散々で、ほとんど記事化されなかったんです。
その失敗から学んだのは、ターゲットオーディエンスに合わせたメディア選定の重要性です。例えば、BtoB製品の場合は業界専門誌や経済メディアが効果的であり、一般消費者向け製品なら生活情報誌やライフスタイルメディアが適しています。
メディア選定の具体的な基準としては以下のポイントを押さえましょう:
- ターゲット層との親和性:そのメディアを実際のターゲット層が閲覧しているか
- 過去の掲載実績:同業他社や類似商品の記事が掲載されているか
- メディアの影響力:業界内での評価や購読者数、WebサイトならUU数など
- 記者の専門性:製品やサービスカテゴリーを担当する専門記者の有無
私の場合、IT製品のプレスリリースを配信する際には、まず主要IT専門メディア、次にビジネスパーソン向け経済メディア、そして製品特性に応じた専門誌という優先順位をつけています。この方法で掲載率が約2倍に上がりました。
業界別・専門メディアへの効果的なアプローチ
業界別のメディアは、一般メディアよりも専門性が高く、その業界に強い関心を持つ読者が集まっています。ここへのアプローチは、一般メディアとは少し異なるテクニックが必要です。
私が健康食品メーカーのPR担当だったとき、最初は一般的なプレスリリースの書き方で健康専門誌にアプローチしていましたが、ほとんど反応がありませんでした。そこで戦略を変え、健康分野の学術的な背景や研究結果を盛り込んだプレスリリースを作成したところ、専門誌からの反応が劇的に改善しました。
専門メディアへアプローチする際の効果的なポイントは:
- 専門的な視点を盛り込む:業界専門用語や最新トレンドへの言及
- データや実証結果を強調:専門メディアは裏付けのある情報を重視
- 業界課題との関連性を明示:その業界が直面している課題の解決策としてのポジショニング
- 担当記者とのリレーション構築:一度きりではなく、継続的な情報提供と関係づくり
実際に化粧品ブランドのプレスリリースでは、「美容成分の浸透率が従来比150%」といった具体的なデータを前面に出したところ、美容専門メディアから多数の問い合わせを受けました。専門メディアは専門的な内容を求めているんですね。
記者クラブと専門誌の活用方法
記者クラブへのアプローチは、特に日本の広報活動において重要な位置を占めています。私が初めて記者クラブに資料を持ち込んだときは緊張しましたが、適切な準備と理解があれば効果的に活用できます。
記者クラブへのアプローチで成功した事例として、ある製造業の会社で新工場設立の発表を担当したときのことです。地元の記者クラブに直接足を運び、工場設立による地域経済への貢献度を具体的な数字と共に提示しました。結果として地元メディア5社が記事化してくれました。
記者クラブと専門誌を効果的に活用するためのポイントは:
- 記者クラブの種類と特性を理解する:
- 地方記者クラブ:地域ニュースに強い関心
- 経済記者クラブ:企業活動や経済動向に注目
- 官庁記者クラブ:規制や政策関連のニュースを重視
- 情報の「届け方」を工夫する:
- 投げ込み:資料を記者クラブに持ち込む方法(初めての場合は事前連絡がベター)
- レクチャー:少人数の記者に詳細説明を行う方法
- 記者会見:重要な発表時に複数の記者を招集する方法
- 専門誌特有のリードタイムを考慮する:
- 月刊誌は1-2ヶ月前、週刊誌は2-3週間前に情報提供が望ましい
- 紙媒体とウェブ版では締切時間が異なることが多い
私がテクノロジー企業で働いていたとき、業界専門誌は掲載までに時間がかかるものの、より詳細な記事を書いてくれることが多いと気づきました。そのため、製品ロードマップに合わせて1-2ヶ月前から情報提供を始め、製品発売日に合わせた記事掲載を実現していました。
デジタルメディアとの効果的な連携方法
デジタルメディアの台頭により、プレスリリース配信の風景は大きく変化しています。オンラインニュースサイトやテックブログなどは従来の媒体とは異なるアプローチが効果的です。
あるスタートアップの担当として、新サービス発表のプレスリリースを配信した際、紙媒体向けの長文リリースと同時に、デジタルメディア向けに画像や動画を豊富に含む資料も用意しました。結果的に、デジタルメディアでの露出が紙媒体の3倍になったことがあります。
デジタルメディアとの効果的な連携のためのポイント:
- 視覚的要素を充実させる:
- 高解像度の製品画像や使用イメージ
- 短い説明動画やデモ映像
- インフォグラフィックスやデータの可視化
- オンライン特性に合わせた情報提供:
- ソーシャルメディア用の短い見出しやキャッチコピー
- 埋め込み用のソースコードやリンク
- オンライン記者会見やウェビナーの開催
- 記事化しやすい形式での情報提供:
- プレスキットのクラウド共有
- 担当者へのオンラインインタビュー機会の提供
- 公開可能な追加データやバックグラウンド情報
私の経験では、デジタルメディアは迅速な情報発信を重視する傾向があります。そのため、プレスリリース配信と同時に問い合わせ対応ができる体制を整えておくことが重要です。一度、準備不足で記者からの質問に即答できなかったことがあり、記事化のタイミングを逃してしまいました。それ以降は、想定Q&Aリストを事前に用意するようにしています。
業界別メディア選定のポイント
業界によって効果的なメディアアプローチは大きく異なります。以下に主要な業界別のポイントをまとめました:
IT・テクノロジー業界:
- 専門技術メディア(日経XTECH、ITmediaなど)
- スタートアップ・ベンチャー関連メディア
- 海外テックメディアの日本版(TechCrunchなど)
- 開発者コミュニティサイト
金融・投資関連:
- 経済専門紙(日経、東洋経済など)
- 金融専門誌(ダイヤモンドZAiなど)
- 投資家向けWebサイト
- フィンテック専門メディア
ヘルスケア・医療:
- 医療従事者向け専門誌
- 健康情報サイト
- 医療機器・製薬業界誌
- 公的機関の情報発信媒体
例えば、私が医療機器メーカーのPR担当だったときは、一般メディアよりも医師向け専門誌や医療従事者向けWebサイトを重視しました。専門性の高い内容を理解してもらえる媒体に注力することで、ターゲットに確実に情報が届きやすくなります。
プレスリリース配信におけるメディア選定とアプローチは、PR活動の成否を左右する重要な要素です。自社の伝えたいメッセージと、そのメッセージを最も必要としている読者がいるメディアをマッチングさせることが鍵となります。これまでの失敗と成功の経験から学んだことは、「配信先を絞り込み、それぞれのメディア特性に合わせたアプローチをする」ということの重要性です。
どんなに素晴らしい内容のプレスリリースでも、適切なメディアに届かなければ効果は半減します。各メディアの特性を理解し、ターゲットオーディエンスを意識した戦略的なアプローチを心がけましょう。そうすることで、プレスリリースの効果を最大限に引き出すことができるはずです。
配信後のフォローアップと効果測定
プレスリリースを配信したら「さあ終わった」と一息つきたくなりますよね。私も初めてPR業務を担当したときは、配信作業自体に精一杯で、その後のフォローアップの重要性を見落としていました。しかし、実際にはプレスリリース配信後の対応こそが、メディア露出を最大化するための重要なステップなのです。
掲載状況の確認と記事化促進の方法
プレスリリース配信から24時間、これは最も重要な時間帯です。私が過去に大手IT企業のPR担当をしていたとき、配信直後の2時間と翌日の朝の掲載確認を怠ったことで、ある記者の誤解に基づいた記事が掲載されてしまったことがありました。その経験から学んだのは、掲載状況の「早期確認」の重要性です。
具体的な掲載確認の手順としては:
- 配信直後(2時間以内): 主要メディアのサイトで検索し、速報記事が出ているかチェック
- 翌日午前中: クリッピングサービスやGoogle Alertsで掲載状況を確認
- 3日後: 週刊誌や専門誌など、編集期間が長いメディアの動向をチェック
掲載が少ない場合は、積極的に記事化を促進することも大切です。ただし、押しつけがましいアプローチは逆効果。私は「追加情報の提供」という形で記者にアプローチするようにしています。例えば:
「先日配信したプレスリリースに関連して、市場データの詳細資料をご用意しました。ご興味がありましたらお送りいたしますが、いかがでしょうか?」
このような控えめなアプローチが、意外にも記者からの反応を引き出すことが多いんですよ。特に専門誌などは締切スケジュールの関係で、すぐには記事化できないケースもあるため、タイミングを考慮した対応が効果的です。
記者からの問い合わせ対応のポイント
プレスリリースが記者の興味を引くと、追加取材の依頼が来ることがあります。この機会を逃さないことが、メディア露出を最大化するポイントです。
私が経験した失敗の一つは、記者からの問い合わせに対する社内の回答プロセスの遅さでした。ある製品発表時、技術的な質問への回答が社内承認で丸1日かかってしまい、記事化のチャンスを逃してしまったのです。この経験から、以下の対応策を実施するようになりました:
- Q&A集の事前準備: よくある質問とその回答を配信前に用意
- 回答の権限委譲: 緊急時に誰が最終判断できるかを明確化
- 即答できない場合の対応: 「○時までに回答します」と具体的な時間を伝える
記者対応で特に重要なのは「スピード」と「正確さ」のバランスです。私の場合、「不明点はあとで補足する」ことを前提に、まず速やかに回答するようにしています。記者の締切に間に合わなければ、どんなに素晴らしい情報も記事にはなりませんからね。
あるグローバル企業のPRを担当していたとき、海外本社の承認を待っているうちに日本の記者の締切が過ぎてしまうケースが頻発していました。そこで「基本的な質問については現地判断で回答できる」というルールを確立したところ、掲載率が約30%向上したという成果がありました。
配信効果の測定と分析手法
「プレスリリースの効果測定」と聞くと、単純に「何件掲載されたか」だけを数える方も多いかもしれません。しかし、本当に意味のある効果測定はもっと多角的です。
私が実践している効果測定の方法は以下のとおりです:
定量的指標
- 掲載数: 媒体タイプ別(オンライン/紙媒体/テレビなど)の掲載件数
- 到達数: 推定閲覧者数・視聴者数(各メディアの公表値から算出)
- 広告換算値: 同じスペース・時間の広告を出した場合のコスト
- ソーシャルシェア数: 掲載記事のSNSでの拡散状況
- 自社サイトへの流入: プレスリリース関連の検索キーワードからの流入増加
特に最後の「自社サイトへの流入」は見落としがちですが、実はとても重要です。あるサービス発表時、GoogleアナリティクスとSearch Consoleで計測したところ、プレスリリース配信後の2週間で関連キーワードからの自然検索流入が3倍に増加したことがありました。
定性的指標
- メッセージの正確さ: 伝えたいポイントが正確に報じられたか
- トーン: 好意的/中立的/批判的な論調の分布
- ターゲット到達: 狙ったターゲット層にリーチしたか
さらに効果的なのは、これらの測定結果を次回のプレスリリースに活かすことです。たとえば、あるクライアントの場合、数字やデータを多く含めたプレスリリースのほうが掲載率が15%高いという分析結果が出たので、次回から意識的にデータを強化したところ、メディア掲載が増加しました。
具体的な測定ツール
効果測定には以下のようなツールを活用すると効率的です:
- クリッピングサービス: PR TimesやNewsPicksなどの配信サービスの掲載レポート機能
- ソーシャルリスニングツール: Meltwater、Brandwatchなど
- ウェブ解析: Google Analytics、Search Console
- メディア価値評価: METRICSなどの専門サービス
私の経験では、特に「Google Search Console」は無料ながら非常に価値のある情報を提供してくれます。プレスリリース配信後、関連キーワードの検索順位や表示回数の変化を追跡することで、SEO効果も測定できるんですよ。
長期的な視点でのフォローアップ戦略
効果的なプレスリリース活動は、単発ではなく継続的な取り組みです。私がある製造業クライアントと3年間取り組んだ事例では、以下のような長期戦略が効果を発揮しました:
- 年間PR計画との連動: 四半期ごとの重点テーマを決め、プレスリリースを計画的に配信
- メディアとの関係構築: 掲載してくれた記者への定期的な情報提供や懇談会の実施
- 過去リリースの活用: 新製品発表時に過去の関連リリースを参照情報として提供
特に「記者との関係構築」は、長期的に見ると非常に重要です。単なる情報提供者ではなく、業界の信頼できる情報源として認識されることで、プレスリリースがなくても取材依頼が来るようになります。
私の場合、メディア担当者とのコミュニケーションを記録するCRMを作成し、「どの記者がどのトピックに関心があるか」を可視化することで、より効果的なアプローチができるようになりました。こうした地道な取り組みが、長期的な露出につながるのです。
配信後のトラブル対応
最後に、配信後のトラブル対応についても触れておきましょう。どんなに慎重に準備しても、想定外の事態は起こりえます。
私が経験した最も大きなトラブルは、製品発表のプレスリリースを配信した直後に、その製品に技術的な欠陥が見つかったケースです。すでに複数のメディアに掲載された後だったため、対応に苦慮しました。
このような場合の対応フローとしては:
- 迅速な事実確認: 問題の範囲と影響を正確に把握
- 訂正文の配信準備: 誤りの内容と正しい情報を明記
- 掲載メディアへの個別連絡: 特に大きく取り上げたメディアには電話でも説明
- 社内報告ルートの確保: 経営層への速やかな状況報告
特に記者への連絡は「隠さない、誠実に、迅速に」が鉄則です。一度信頼を失うと、今後のプレスリリースも取り上げてもらえなくなる可能性があります。
あるIT企業のケースでは、データの誤りを指摘されたにもかかわらず対応が遅れたため、その後1年近く同じ記者に記事化してもらえなくなったという苦い経験もあります。トラブルの大小にかかわらず、誠実で迅速な対応が何よりも重要なのです。
プレスリリース配信後のフォローアップと効果測定は、地味な作業に思えるかもしれませんが、実はPR活動全体の成果を左右する重要なプロセスです。配信して終わりではなく、その後の対応までを一連の流れとして捉え、サイクルを回していくことで、PR活動の効果は格段に高まります。
失敗と成功を繰り返しながら見えてきたのは、「配信はPRのスタートラインに過ぎない」という真理です。ぜひ皆さんも、配信後の活動にも力を入れて、プレスリリースの効果を最大限に引き出してください。
よくある失敗とトラブル対策
プレスリリース配信は一見単純な作業に思えますが、思わぬところでトラブルが発生することがあります。私自身、PR担当として10年以上の経験の中で、いくつもの「しまった!」という瞬間を経験してきました。ここでは、多くの企業が陥りがちなミスと、それを防ぐための実践的な対策をご紹介します。
配信タイミングの失敗事例と対策
配信タイミングの失敗は、せっかくの情報が埋もれてしまう大きな原因です。あるIT企業のプレスリリース配信を担当したとき、金曜日の夕方に重要な製品発表のリリースを配信してしまい、週末にかけてメディアの注目がほとんど集まらなかった苦い経験があります。
よくある失敗パターンとしては:
- 週末直前(金曜午後)の配信
- 祝日や大型連休前の配信
- 巨大イベントや大きなニュースと重なる日の配信
- 深夜や早朝の配信
【対策】
メディア関係者は一般的に「火曜日から木曜日の午前10時から午後2時」の時間帯が最も情報をチェックしやすいと言われています。特に重要なプレスリリースは、この「ゴールデンタイム」を狙って配信するのがベストです。
また、配信前に主要メディアのスケジュールや大きなイベント予定をチェックする習慣をつけることで、他の大きなニュースと被るリスクを減らせます。私は常に翌月のカレンダーに主要イベントや競合他社の発表予定などをマークし、「空いている日」を見つけるようにしています。
さらに、緊急性の低いリリースなら、あえて「ニュースが少ない日」を狙うという逆転の発想も有効です。8月のお盆期間や年末年始など、通常は避けられる時期でも、競合が少ないためにかえって注目を集めやすいことがあります。
誤配信・誤字脱字の防止策
プレスリリースの誤配信や誤字脱字は、企業の信頼性に直結する問題です。以前、ある製品の価格を1桁間違えて記載したプレスリリースが配信されてしまったケースを目の当たりにしました。顧客からの問い合わせが殺到し、訂正リリースを出すまでの数時間は文字通り地獄でした。
【防止策】
- 複数人によるクロスチェック体制の構築
私が実践している方法は「3人チェック制」です。内容の専門家、広報の視点、そして第三者(できれば非専門家)の視点でチェックすることで、専門的な誤りから一般の人が気になる違和感まで、幅広くカバーできます。
- チェックリストの活用
以下のようなチェックリストを作成し、配信前に必ず確認するようにしています:
- 日付・時間は正確か
- 数字(価格、割合、日付等)に誤りはないか
- 人名・社名・役職名のスペルや敬称は正確か
- 商標表記(®、™など)は適切か
- リンク先は正しく機能するか
- 画像は適切な解像度で添付されているか
- 問い合わせ先の電話番号・メールアドレスは最新か
- 音読確認
目で見るだけでなく、実際に声に出して読むことで、不自然な表現や読みにくい文章を発見できます。私自身、この方法で多くの誤りを事前に発見できた経験があります。
- 配信前の「クールダウン期間」を設ける
可能であれば、最終チェック完了から実際の配信まで、数時間〜一晩の時間を空けることをおすすめします。一度離れた目で見直すことで、思わぬ発見があることが多いのです。
緊急時の配信中止と訂正対応
どれだけ注意していても、「配信してしまった後に重大な誤りに気づく」という事態は起こりえます。以前、ある企業の製品発表リリースで、まだ最終承認が下りていない情報が含まれていることに、配信直後に気づいたことがありました。
【対応策】
- 緊急対応フローの事前準備
緊急時に慌てないよう、以下のような対応フローを事前に決めておくことが重要です:
- 誤りの重大度判断基準(訂正が必要なレベルか否か)
- 誰が判断を下すのか(決裁権者は誰か)
- 訂正リリース配信の手順
- メディア個別連絡の方法
- 社内関係者への報告ルート
- 素早い対応と透明性の確保
誤りに気づいたら、隠さずに素早く対応することが信頼回復の鍵です。具体的には:
- 配信サービスの「配信中止」機能の活用(可能な場合)
- 訂正リリースの迅速な配信(24時間以内が望ましい)
- 訂正箇所を明確に示し、訂正理由を簡潔に説明
- 必要に応じて主要メディアに個別連絡
- 訂正リリースのテンプレート準備
緊急時にスムーズに対応できるよう、訂正リリースのテンプレートを事前に用意しておくと安心です。以下のような構成がおすすめです:
【訂正】○○に関するプレスリリースの一部訂正について
平素より弊社へのご高配を賜り、誠にありがとうございます。
本日○時○分に配信いたしました「○○に関するプレスリリース」におきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。
【訂正箇所】
(誤)○○○○
(正)○○○○
関係者の皆様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
さいごに
プレスリリース配信の世界は奥が深く、正直なところ私も初めはかなり苦労しました。自社の大事なニュースを効果的に届けたいという思いと裏腹に、配信後の沈黙に落胆した経験は一度や二度ではありません。そんな試行錯誤を重ねてきた経験から、最後に押さえておきたいポイントをお伝えします。
何よりも大切なのは、プレスリリース配信は「ゴール」ではなく「スタート」だということです。せっかく時間をかけて作成したプレスリリースも、適切な配信とフォローアップがなければ、その価値を十分に発揮できません。まるで丁寧に育てた植物に水やりを忘れるようなものです。
私が実際に経験して効果的だったのは、配信方法を固定化せず、ニュースの内容や目的に応じて柔軟に変えていくことでした。大きなニュースリリースであれば配信サービスを使った一斉配信と個別フォローの併用、専門性の高い話題であれば業界メディアへの個別アプローチというように、状況に応じた使い分けが重要なんですよね。
また、メディアとの信頼関係構築も見逃せないポイントです。「いつも役立つ情報を提供してくれる企業」として認識されていれば、プレスリリースの採用率も格段に上がります。あるとき、長期的に関係構築していた記者から「御社のリリースは必ず目を通すようにしています」と言われたときは、地道な努力が報われた瞬間でした。
効果測定についても、ぜひ習慣化してください。単なる掲載数だけでなく、どのメディアでどのように取り上げられたか、その結果としてウェブサイトへのアクセスやお問い合わせにどう影響したかまで追跡できると理想的です。こうしたデータの蓄積が、次回以降のプレスリリース戦略の改善につながります。
それから、失敗を恐れずにトライ&エラーを繰り返すことも大切です。私自身、配信タイミングを間違えて重要なニュースの露出が大幅に減ってしまったり、リリース内の誤植に気づかず配信してしまったりと、様々な失敗を経験してきました。でもそれらの経験が今の私のノウハウになっています。
最近ではSNSとの連携も欠かせません。プレスリリースをメディアに配信すると同時に、自社のSNSでも情報発信することで相乗効果が生まれることがよくあります。メディアで取り上げられた記事をSNSでシェアすることで、さらに露出を拡大できるんですよね。
そして何より、プレスリリース配信は「ゴール」ではなく「手段」だということを忘れないでください。最終的に伝えたいメッセージが適切なターゲットに届き、望ましいアクションにつながることが本当の成功です。
この記事で紹介した方法やテクニックは、決して完璧な解決策ではありません。業界や企業の特性、目的によって最適なアプローチは異なります。ぜひ自社の状況に合わせてカスタマイズし、独自のプレスリリース配信メソッドを築いていってください。
最後に、プレスリリース配信は一朝一夕で極めることはできません。日々の積み重ねと継続的な改善が重要です。この記事が皆さんのプレスリリース配信の質を高める一助となれば幸いです。効果的な配信により、あなたの企業の素晴らしいストーリーが多くの人に届きますように。
みなさんのプレスリリース配信に関する質問や成功体験があれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。お互いの知見を共有することで、さらに効果的な情報発信ができるようになりますよね。これからもプレスリリース関連の最新情報や実践的なノウハウをお届けしていきますので、ぜひブックマークやSNSでのフォローもよろしくお願いします。