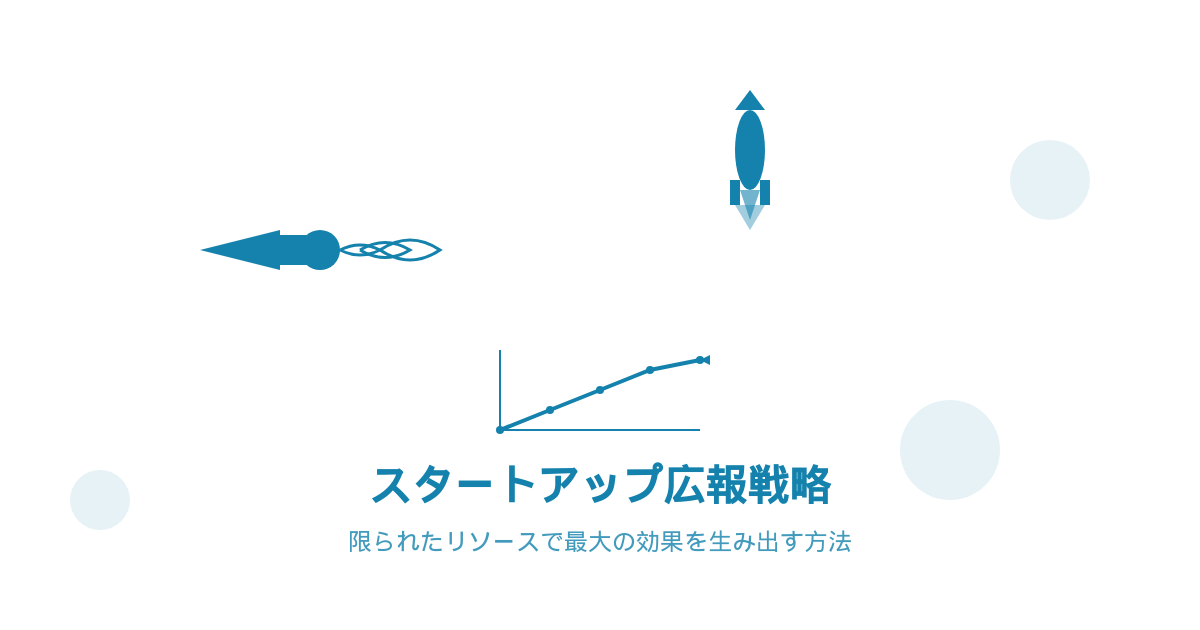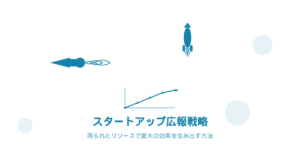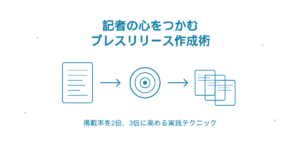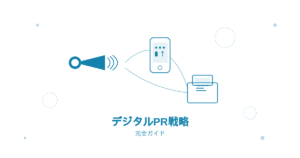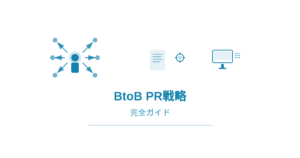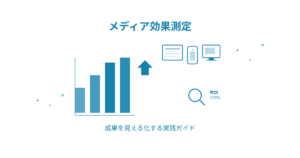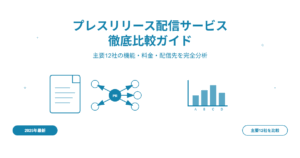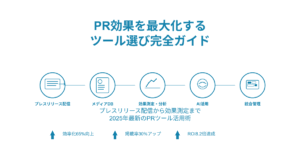「広報活動をどう始めればいいのか分からない」「限られたリソースで効果的なPRを実現したい」。スタートアップの広報担当者なら、誰もが直面するこうした課題。実は日本のスタートアップの約70%が、効果的な広報戦略を持たないまま事業を進めているというデータもあります。これはチャンスでもあるんです。
私自身、ベンチャー企業の広報担当として働いていた頃、予算も人員も限られた中で「どうすれば効果的に会社の魅力を伝えられるのか」と悩み続けました。メディアに取り上げられたいのに連絡しても返事がこない。プレスリリースを出しても反応がない。そんな日々の繰り返しでした。
しかし、さまざまな試行錯誤と失敗を経て見えてきたのは、スタートアップだからこそできる広報の形。大企業のような潤沢なリソースがなくても、創業ストーリーや情熱、機動力を活かした戦略的なアプローチで、確実にメディアの心を掴むことができるんですね。➡️ 関連記事:「PR効果最大化ツール5つの選定基準|失敗しない導入のコツを解説」
本記事では、スタートアップならではの特性を活かした実践的な広報戦略と、成長フェーズに応じた具体的なアプローチ方法をご紹介します。これからスタートアップの広報を担当する方はもちろん、すでに活動を始めているけれどなかなか成果が出ないという方にも、明日から使える具体的なテクニックをお伝えします。
どんな小さなスタートアップでも、正しいアプローチさえ知っていれば、限られたリソースで最大限の広報効果を生み出すことができます。一緒に、効果的なスタートアップPR戦略を学んでいきましょう。
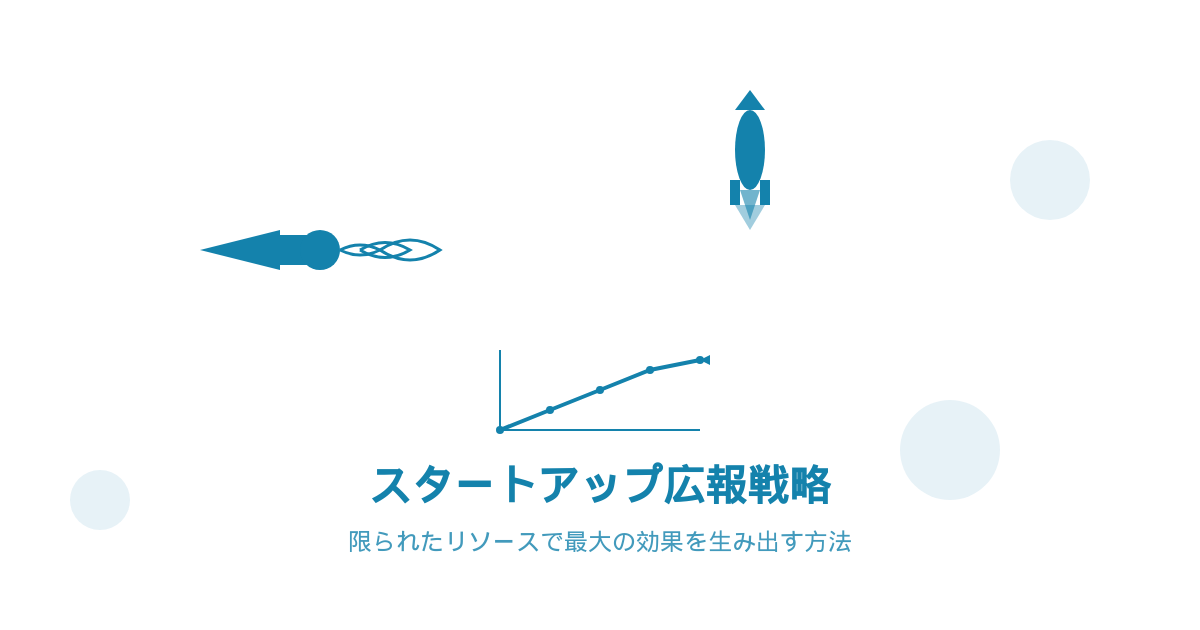
スタートアップ広報の基本戦略と重要性
スタートアップの広報担当になって最初に突き当たる壁は「限られたリソースでどう効果的な広報活動をすべきか」という課題です。私自身、ベンチャー企業の広報担当として働いていた頃、予算も人員も少ない中で苦労した経験があります。最初の数ヶ月は手探り状態で、効果が見えないまま時間だけが過ぎていくことにもどかしさを感じていました。
しかし、試行錯誤を重ねる中で気づいたことがあります。スタートアップの広報活動は、大企業の広報活動とは根本的に異なるアプローチが必要だということです。限られたリソースを最大限に活かすためには、自社の現在のフェーズを正確に理解し、そのフェーズに合った戦略を立てることが不可欠なのです。
成長フェーズ別の広報戦略
スタートアップの成長フェーズは大きく分けると「シード期」「アーリー期」「ミドル期」「レイター期」の4つに分けられます。それぞれのフェーズで広報の目的や対象、手法が異なってきます。
シード期(創業〜プロダクト開発中):この段階では、主に投資家や将来の協業先へのアピールが中心となります。自社のビジョンや解決する社会課題、創業ストーリーなどを効果的に伝えることが重要です。私がある健康テック系のスタートアップを支援していた時は、創業者の「医療格差をなくしたい」という強い想いを中心にストーリーを組み立て、専門メディアに取り上げられたことで、シードラウンドの資金調達につながったケースがありました。
アーリー期(プロダクト提供開始〜初期顧客獲得):この段階では、自社サービスの認知拡大と初期ユーザー獲得が目標となります。プロダクトの特徴や他社との差別化ポイントを明確に伝え、実際に使ってもらうことを促進します。この時期はプレスリリースだけでなく、ユーザーの声や初期データを活用した発信も効果的です。
ミドル期(事業成長・拡大期):ユーザー基盤が徐々に広がり、サービスも安定してくるこの時期は、ブランド価値の向上や業界内でのポジショニング確立が重要になります。データに基づく市場分析や業界トレンドについての見解を発信することで、業界内での存在感を高めていくアプローチが有効です。
レイター期(急成長〜IPO準備期):この段階では、持続的な成長を示しながら、社会的信頼性を高めていくことが求められます。社会貢献活動や経営者のビジョン発信など、より幅広いステークホルダーを意識した広報活動を展開します。
私が関わったあるフードテック系スタートアップでは、成長フェーズに合わせて広報戦略を見直したことで、大きな効果が生まれました。アーリー期には食の安全性に関する独自調査結果を発表し、ミドル期に入ると食品ロス削減の社会的インパクトを強調する戦略に切り替えたところ、メディア露出だけでなく投資家からの関心も高まり、事業拡大のきっかけとなったのです。
リソース制約下での効果的な情報発信方法
限られた予算と人員の中で効果を最大化するには、「選択と集中」が鍵となります。全方位的な広報活動は避け、自社のフェーズと目標に最適なチャネルと手法に集中することが重要です。
プレスリリースの効率的な活用:少ない予算でも大きな効果を得るには、プレスリリースの質と配信タイミングが重要です。私の経験から言うと、記者が興味を持ちそうな「ニュース性」と「データの裏付け」を盛り込むことが大切です。過去に担当したBtoBサービスのスタートアップでは、単なる機能アップデートのリリースではなく、「業界の課題をデータで可視化し、その解決策を提示する」形でプレスリリースを構成したところ、業界メディアから多数の問い合わせがあり、結果的に3つの専門メディアに掲載されました。
ソーシャルメディアの戦略的活用:全てのプラットフォームに手を出すのではなく、自社のターゲットユーザーが最も活用しているチャネルに集中することが効果的です。ただやみくもに投稿するのではなく、投稿カレンダーを作成し、計画的に発信することをおすすめします。実際、私が関わったあるB2Cスタートアップでは、Instagramに集中し、週3回の定期投稿と月1回のインフルエンサーコラボという明確なリズムを作ったところ、6か月で自然フォロワーが5倍に増加しました。
オウンドメディアの活用:限られたリソースの中では、自社ブログやnoteなどを活用した情報発信も有効です。特に技術系のスタートアップでは、エンジニアに技術ブログを書いてもらうことで、専門性の高い情報発信ができ、採用にも良い影響を与えることがあります。ただ、続かないブログは逆効果になることもあるので、持続可能な更新頻度を設定することが大切です。
投資家・メディア・ユーザーへの価値提案の考え方
広報活動を効果的に進めるには、情報の受け手によって伝えるべき内容を変える必要があります。これは私がベンチャー企業の広報担当時代に痛感したことです。
投資家向け:投資家が最も知りたいのは「将来性」と「実現可能性」のバランスです。市場規模や成長率などのマクロデータと、自社の独自性や成長指標を組み合わせて伝えることが重要です。過去に資金調達のプレスリリースを作成した際、単に「○○億円調達しました」という事実だけでなく、「なぜこの事業に投資価値があるのか」「調達資金で何を実現し、どう成長するのか」という視点を盛り込むことで、後続の投資家からの問い合わせが増えたケースがありました。
メディア向け:記者が求めているのは「読者に価値のある新しい情報」です。自社のサービスだけでなく、業界の課題や最新トレンドなど、より広い文脈で情報を提供することで取り上げられる確率が高まります。私の経験では、単なる製品発表より「業界の課題×データ×解決策」という構成で情報を提供すると、記者の反応が格段に良くなりました。
ユーザー向け:最終的に商品やサービスを利用するユーザーには、具体的なベネフィットやユースケースを分かりやすく伝えることが重要です。「何ができるか」より「どんな問題が解決するか」「どう生活が便利になるか」という視点で情報を構成します。
広報活動は継続が命です。一度メディアに取り上げられただけで終わりではなく、定期的にコンタクトを取り、関係を構築していくことが重要です。私自身、過去に担当したスタートアップでは、四半期に一度はニュースレターを記者に送り、業界の動向についてのコメントを添えるという取り組みを行いました。最初は反応が薄かったのですが、継続することで徐々に関係が構築され、記者から「この件についてコメントが欲しい」と逆に声をかけてもらえるようになったのです。
スタートアップの広報活動は、大企業のそれとは異なり、リソースの制約がある中で最大限の効果を生み出すことが求められます。しかし、その制約をむしろ強みに変え、自社の独自性や機動力を活かした広報戦略を展開することで、大企業にはない存在感を示すことができるのです。この基本戦略を理解し、自社のフェーズに合わせた施策を選択することが、スタートアップ広報成功の第一歩となるでしょう。
効果的なブランドストーリー構築
スタートアップの広報活動において、もっとも重要な武器の一つが「ブランドストーリー」です。私が初めてスタートアップの広報支援を手がけたとき、どんなに素晴らしい技術やサービスを持っていても、「なぜ」その事業に取り組んでいるのかという物語がなければ、記者やステークホルダーの心に響かないことを痛感しました。
今回は、リソースの限られたスタートアップだからこそ活用すべき、効果的なブランドストーリー構築の方法について、実践的な視点からお伝えします。
創業の原点を掘り下げる
スタートアップのブランドストーリーで最も価値があるのは「創業の原点」です。大企業と違い、スタートアップの多くは創業者の強い想いから生まれています。この「なぜこの事業を始めたのか」という原点こそが、他社には真似できない唯一無二の資産なんです。
以前サポートした医療系スタートアップでは、創業者が家族の病気をきっかけに事業を立ち上げたという経緯がありました。最初は「個人的な話は控えたい」と躊躇していましたが、その体験談をストーリーの中心に据えたところ、メディアの反応が劇的に変わったのです。数字やスペックだけでは伝わらない「人間らしさ」が、ブランドに命を吹き込みました。
ポイントは、創業の原点を時系列で整理すること。「どんな課題を目の当たりにしたのか」「どんな気づきがあったのか」「その解決のためにどう行動したのか」という流れを意識して構成すると、より共感を生みやすくなります。
共感を呼ぶ「課題」と「解決策」の明確化
効果的なブランドストーリーの第二の要素は、「社会課題」と「独自の解決策」の組み合わせです。これは単なる「困っている人がいるから解決します」という表面的なものではなく、創業者がなぜその課題に心を動かされたのか、どうしてその解決策に至ったのかという深い洞察が必要です。
私が関わったあるフードテックスタートアップでは、当初「食品ロス削減」という大きな課題を掲げていましたが、なかなかメディアの興味を引けずにいました。そこで創業者の経験を掘り下げたところ、実は地方の農家だった祖父の苦労を間近で見てきたことが原点だったのです。
この個人的な原体験と社会課題を結びつけ、「祖父のような生産者の苦労を減らしながら食品ロスも解決する」というストーリーに再構築したところ、多くのメディアで取り上げられるようになりました。課題と解決策を「人」を通して描くことで、抽象的な社会問題が具体的な物語に変わったのです。
実践するときのコツは、以下の3つの問いを深堀りすることです:
- なぜあなた(創業者)がこの課題に取り組むのか?
- 既存の解決策では何が足りなかったのか?
- あなたの解決策は何が違うのか?
これらの問いに対する答えを言語化することで、ただの事業紹介ではなく、共感を呼ぶストーリーになります。
数字とエピソードを組み合わせる
ブランドストーリーを語る上で、「数字」と「エピソード」のバランスが重要です。数字だけだと冷たい印象になりますし、エピソードだけだと具体性に欠けてしまいます。
私が以前担当したヘルスケアスタートアップでは、「利用者の89%が改善を実感」という数字がありました。ただ、これだけではインパクトに欠けます。そこで、実際のユーザーである60代女性の具体的なストーリーを加えました。「30年間悩み続けた症状が2ヶ月で改善し、久しぶりに孫と一緒に公園で遊べるようになった」というエピソードです。
これにより抽象的な数字が具体的な人生の変化として伝わり、メディアの記事では見出しに使われるほどのインパクトがありました。数字は信頼性を、エピソードは共感性を高めるのです。
効果的なバランスとしては、「大きな課題を示す数字」→「個人的なエピソード」→「解決策による変化を示す数字」→「具体的な成功事例」という流れが理想的です。
ビジョンと現実のギャップを正直に語る
スタートアップのブランドストーリーで見落としがちなのが、「理想と現実のギャップ」です。大きなビジョンを掲げつつも、現時点での限界や課題を正直に認めることで、かえって信頼性が増すことがあります。
ある環境テック系のスタートアップでは、最初は「革命的な技術で環境問題を解決する」と強気のメッセージを出していました。しかし、技術的な課題も多く、記者からの鋭い質問にうまく答えられずにいました。
そこで戦略を変え、「理想の未来に向けて挑戦している途上で、こんな課題にぶつかっている」という正直なストーリーに切り替えたところ、むしろ応援してくれるメディアが増えたのです。完璧を装うよりも、挑戦する姿勢と謙虚さのバランスが、スタートアップらしさとして好意的に受け止められました。
実践のポイントは、以下のフレームワークを意識することです:
- 「目指す理想の世界」を明確に描く
- 「現状の課題と限界」を正直に認める
- 「それでも挑戦し続ける理由」を熱く語る
ブランドストーリーを広報素材として活用する方法
せっかく構築したブランドストーリーも、効果的に活用しなければ意味がありません。私の経験から、以下の4つの活用方法が特に効果的です。
1. ティザー動画の制作
短い1-2分のビデオで創業ストーリーを語る「ティザー動画」は、限られた予算でも大きな効果を発揮します。スマホとシンプルな編集アプリでも十分なクオリティが出せるようになった今、ハードルはとても低くなっています。
あるD2Cスタートアップでは、創業者自身がスマホで撮影した2分間の動画を公開したところ、リーチは少なかったものの、視聴したジャーナリストからの反応率が非常に高かったという事例があります。文字では伝わらない創業者の表情や声のトーンが、共感を生み出したのです。
2. メディアキットの作成
忙しい記者に対して、あなたの会社を素早く理解してもらうための「メディアキット」は必須アイテムです。これには以下の要素を含めると効果的です:
- 創業ストーリーの要約(1ページ)
- 主要メンバーの紹介と個人的な動機
- 解決しようとしている課題の具体的なデータ
- 実際のユーザーの声(許可を得たもの)
- 高解像度の写真や素材(自由に使えるもの)
これを1つのPDFにまとめておくだけで、記者からの問い合わせ対応の効率が格段に上がります。
3. インタビュー記事の戦略的な配置
創業ストーリーを語ったインタビュー記事は、他の記事への引用元として機能します。しかしただ受動的に応じるだけでなく、戦略的に配置することが重要です。
例えば、業界専門メディアでまず詳細なインタビューを受け、そこで語ったストーリーを大手メディアへのアプローチ時に引用できるようにする、といった段階的な展開が効果的です。サポートしたスタートアップでは、このアプローチで小さな業界誌のインタビューが最終的に全国紙の記事につながった例もあります。
4. ブランドストーリーの継続的なアップデート
最後に忘れてはならないのが、ブランドストーリーは「生き物」だということ。成長の過程で得た気づきや、新たな挑戦を定期的に追加していくことで、メディアに継続的にアプローチする材料になります。
「創業1周年で見えてきたこと」「ユーザー100人から学んだこと」など、節目ごとにストーリーをアップデートし、再発信する習慣をつけることで、メディア露出の機会を増やせます。
ブランドストーリー構築の落とし穴
最後に、スタートアップがブランドストーリーを構築する際によくある落とし穴についてお伝えします。
まず「技術や機能の説明に終始してしまう」こと。これは特に技術系スタートアップによく見られる問題です。素晴らしい技術があっても、それが「人々の生活をどう変えるのか」という視点がなければ、多くの人の心には響きません。
次に「ありきたりな表現に頼ってしまう」こと。「世界を変える」「革新的な」といった抽象的な表現は、具体性がないため印象に残りにくいです。どんな世界を、どのように変えるのかを具体的に描くことが大切です。
そして「創業者だけの物語になってしまう」こと。確かに創業者の想いは重要ですが、チームメンバーやユーザーの視点も取り入れることで、より多面的で説得力のあるストーリーになります。
これらの落とし穴を避けるためには、常に「このストーリーは第三者の心を動かすか?」という視点でチェックすることが大切です。自社内だけでなく、信頼できる外部の人に聞いてもらい、正直な感想をもらうことをおすすめします。
スタートアップならではのPR手法
スタートアップの広報担当として活動し始めた当初、私は「大手企業のやり方をそのまま真似れば良いのでは?」と安易に考えていました。でも実際に取り組んでみると、予算も人員も時間も限られているスタートアップには、独自のアプローチが必要だということを痛感したんです。今日は、そんな試行錯誤の末に見つけた「スタートアップだからこそできる」PR手法をご紹介します。
予算ゼロから始めるニュースバリューの作り方
最初に直面した壁は「お金をかけずにどうやってメディアの注目を集めるか」という課題でした。プレスリリース配信サービスすら予算が取れず、途方に暮れていたときに気づいたのは、「スタートアップならではのストーリー」の価値です。
私たちが取り組んだのは、創業者の「なぜこの事業を始めたのか」という原体験を掘り下げること。ただの会社紹介ではなく、社会課題に対する熱意や、従来のやり方への疑問など、創業者の「人間ドラマ」を前面に出したプレスリリースを作成しました。
例えば、ある教育系スタートアップの広報支援をした際は、創業者の「地方出身で教育格差を自分自身が経験した」というバックストーリーを中心に据えました。この取り組みが奏功し、予算ゼロながら全国紙の教育面で取り上げられたのです。そのときの喜びは今でも忘れられません。
ポイントは以下の3つです:
- 既存市場への挑戦性を強調する: 「〇〇業界の常識を覆す」というアングルは記者の興味を引きます
- 創業者の原体験を掘り下げる: 個人的な動機やドラマがメディアストーリーになります
- 数字で語る革新性: 「従来比30%効率化」など、具体的な数値があるとニュース価値が高まります
少人数チームでの効率的な広報サイクルの回し方
スタートアップでは私一人が広報担当というケースもあり、すべてを完璧にこなすのは物理的に不可能でした。そこで編み出したのが「選択と集中」の広報サイクルです。
具体的には、毎月1つだけニュースを作る「マンスリーニュース計画」を実践しました。例えば:
- 1月:新サービス発表
- 2月:ユーザー数実績発表
- 3月:新機能リリース
- 4月:業界調査結果発表
このサイクルで計画的にニュースを生み出し、それぞれに全エネルギーを注ぎました。一度に多くのことをするのではなく、一つのニュースに集中することで、少ないリソースでもインパクトのある発信ができるんです。
また、プレスリリースの作成も「テンプレート化」が効果的でした。具体的には:
- 見出し部分: 「[業界]の課題を解決する[新発想]を[会社名]が開発」という定型フォーマット
- 本文構成: 「課題→解決策→具体的な製品・サービス→市場への影響」の流れを統一
- 引用コメント: 創業者・CEOのコメントは「社会的意義→個人的な思い→今後の展望」の順で構成
この型を作っておくことで、情報を埋めていくだけで一定水準のプレスリリースが完成するようになりました。以前は1本書くのに丸2日かかっていたのが、半日程度で完成するようになったんです。さすがにほっとしましたね。
スタートアップの弱みを強みに変えるソーシャルメディア戦略
大手企業と比べると知名度もフォロワー数も圧倒的に不利なスタートアップ。でも、逆にそれが「機動力」と「人間味」という武器になることに気づきました。
私が実践して効果的だったのは、「顔の見える発信」です。特に創業初期は、企業アカウントだけでなく、創業者や社員の個人アカウントからの情報発信が非常に有効でした。企業ページでは数十いいねだった投稿が、創業者の個人アカウントから発信すると数百いいねがつくこともあったんです。
例えば、あるBtoBスタートアップでは、創業者がLinkedInで「創業に至るまでの苦労話」「プロダクト開発の裏話」を定期的に投稿していました。これが業界内で共感を呼び、徐々にフォロワーが増加。そこから投資家とのコネクションも生まれたのを目の当たりにしました。
また、スタートアップならではの「意思決定の速さ」を活かし、話題のニュースに対して素早くコメントすることで、タイムリーな存在感を示すことも可能です。例えば、業界に関連する法律が改正されたときに、その日のうちに「スタートアップの視点から見たインパクト」をブログやSNSで発信することで、メディアからの取材依頼につながったケースもありました。
具体的な施策としておすすめなのは:
- 創業者の個人ブランディング: 専門性を活かした発信で業界内での存在感を高める
- オフレコ感のある情報発信: 「実は今日こんなことがありました」といった舞台裏の共有
- ユーザー・顧客との対話: コメントへのレスポンスを丁寧に行い、会話を生み出す
リソースを最大化する「エバーグリーンコンテンツ」の活用法
スタートアップでは、毎月大量のコンテンツを生み出す余裕はありません。そこで効果的だったのが「一度作って長期間活用できるコンテンツ」、いわゆる「エバーグリーンコンテンツ」の戦略的活用です。
例えば、業界の課題や動向をまとめた「ホワイトペーパー」は、作成に時間がかかる半面、一度作れば長期間にわたって以下のように活用できます:
- メディアへの情報提供資料
- セミナー・ウェビナーの元ネタ
- SNS投稿の連続コンテンツ
- リード獲得用のダウンロード資料
- 営業担当者の提案資料
私が関わったITスタートアップでは、「○○業界DX実態調査レポート」を作成しました。初めは100人程度のアンケート調査でしたが、このレポートを基に業界メディアに掲載され、さらにそれがきっかけで大手メディアの取材につながりました。結果的に半年間にわたって、このレポートが様々な形でPR効果を生み出したのを見て、コンテンツの「資産価値」を実感しました。
別のケースでは、創業者のこれまでの経験や知見をまとめた「ノウハウ集」が、SNSでシェアされる価値あるコンテンツとなり、自社メディアへのトラフィック増加に貢献しました。当初は「こんな基本的なことを書いて価値があるのか」と不安でしたが、意外にも業界初心者から「非常に分かりやすい」と高評価を得たんです。
低予算で実現するPR効果測定の方法
「効果が測定できない広報活動は改善できない」と言われますが、高額なメディアモニタリングツールを導入する余裕がないスタートアップでは、どうすれば効果測定ができるのでしょうか。
私が実践してきた低コストでのPR効果測定方法は以下のとおりです:
- Google Alertsの活用: 自社名や創業者名、キーフレーズをセットして無料で記事掲載を把握
- UTMパラメータの徹底: プレスリリースやSNS投稿にはすべてUTMパラメータを付与して流入を追跡
- 簡易アンケートの実施: 問い合わせフォームに「どこで知りましたか?」の項目を追加
これらの方法で収集したデータを、Googleスプレッドシートで一元管理。その結果、「どの種類のプレスリリースが記事化されやすいか」「どのメディアからの流入がコンバージョンにつながりやすいか」といった傾向が見えてきました。
特に効果があったのは、定量データだけでなく、「記事の論調」や「SNSでのコメント内容」といった定性データも記録することです。あるプロダクトローンチ時には、数値上は同じような露出量でも、「革新的」「使いやすそう」といったポジティブな反応が多かった記事と、単なる事実紹介に留まる記事では、後日のサービス申込数に大きな差があったことがわかりました。
このように、高価なツールがなくても、工夫次第で意味のある効果測定と施策改善のサイクルは回せるんです。最初は手作業で大変でしたが、徐々に効率化して今では週に30分程度の作業で済むようになりました。
メディアリレーション構築のポイント
メディアとの関係構築は、スタートアップ広報の成功に欠かせない要素です。私自身、あるベンチャー企業の広報担当として働いていた頃、最初は「どうやって記者さんにアプローチすればいいの?」と途方に暮れていました。今回は、そんな経験から学んだ、効果的なメディアリレーション構築のコツをお伝えします。
記者との初期コンタクト—失敗から学んだ教訓
最初のメディアコンタクトで私がやってしまった失敗は、「自社の魅力を伝えよう」と意気込むあまり、一方的に情報を押し付けてしまったことでした。ある業界メディアの記者に初めてアプローチした際、社長が考えた「革新的なビジョン」について熱く語りましたが、記者からは「それで、ニュースは何ですか?」と冷静に切り返されてしまいました。
この経験から学んだのは、記者が求めているのは「ニュース価値」であり、単なる企業PRではないということ。記者との初めての接点では、以下のポイントを意識するようになりました:
- 自社の話をする前に、記者の担当領域や興味のある分野を調査する
- 初回は「売り込み」ではなく「関係構築」が目的と心得る
- 具体的で明確なニュース要素(新規性・独自性・社会的意義)を整理してから連絡する
これらを意識するようになってから、徐々に関係性が構築できるようになりました。特に効果的だったのは、記者の過去の記事をきちんと読み込み、「○○の記事に感銘を受けました」と具体的に伝えることです。記者も自分の記事を読んでくれている人には心を開きやすいものです。
スタートアップ担当記者とのコネクション作り
多くのメディアには、スタートアップやベンチャー企業を専門に取材する記者がいます。こうした記者との関係構築は、特に重要です。私の経験から、スタートアップ担当記者とのコネクション作りで効果的だった方法をご紹介します。
1. スタートアップイベントや交流会の活用
スタートアップ関連のピッチイベントやミートアップは、記者と自然な形で出会える貴重な機会です。あるスタートアップカンファレンスで、たまたま隣に座った方が大手経済紙の記者だったことがあります。その場では会社の売り込みはせず、業界動向について意見交換をするだけに留めました。後日、その記者から「あのときの話が興味深かった」とメールをいただき、関係構築のきっかけになったのです。
記者との対話で意識したいのは、自社の宣伝ではなく、業界の課題や展望について意見交換すること。記者にとって価値ある情報や視点を提供できれば、自然と関心を持ってもらえます。
2. 記者の専門分野に合わせたアプローチ
私が特に効果的だと感じたのは、記者の専門性や興味に合わせた情報提供です。例えば、テクノロジー系スタートアップを担当する記者なら、最新技術トレンドに関する非公開情報を先んじて共有するなど、その記者ならではの記事になりそうな切り口を提案します。
以前、AI関連のスタートアップを取材している記者に、当社のAI技術を使った新サービスについて情報提供したところ、「同業他社との違いは?」と鋭い質問がありました。ここで一般論を述べるのではなく、「実はこの技術は○○という特許技術を応用していて、従来のAIよりも処理速度が30%速い」という具体的なデータと差別化ポイントを伝えたところ、興味を持ってもらえました。
3. タイミングを見極めたアプローチ
記者へのアプローチのタイミングも重要です。週刊誌や月刊誌の締切日、大型イベントの前後など、記者が多忙な時期を避けることが大切です。また、朝一番や夕方の忙しい時間帯も避けるべきでしょう。
私の経験では、火曜日か水曜日の午前中がもっとも記者の反応が良かったです。月曜は週始めで忙しく、金曜は週末の記事準備で余裕がない場合が多いためです。これは業界やメディアによって異なる可能性がありますが、少しずつ最適なタイミングを見つけていくことが大切です。
業界メディアへのアプローチ方法
大手メディアだけでなく、業界専門メディアとの関係構築も非常に重要です。実際、私たちのようなスタートアップにとっては、まず業界メディアで取り上げられることが、大手メディアへの足がかりになることも多いのです。
1. 業界特有の課題に対するソリューション提案
業界メディアの記者は、その分野の専門知識を持っているため、表面的な話では興味を持ってもらえません。私たちが取り組んだのは、業界特有の課題に対して、具体的にどう解決するかを示すアプローチです。
例えば、物流業界の専門メディアに対しては、「単なるITツール導入」ではなく「人手不足という業界課題に対して、当社のシステムを導入した結果、A社では作業時間が25%削減された」という具体的な成果を伝えることで記事化につながりました。
2. データや調査結果の提供
記者が飛びつきやすい情報として、独自のデータや調査結果があります。予算の限られたスタートアップでも、自社サービスのユーザーデータを分析するだけで、興味深い調査結果を生み出せることがあります。
私たちは、自社アプリの利用データを分析した「○○業界におけるデジタル化の進展度調査」をまとめ、業界メディアに提供したことがあります。自社PRを前面に出さず、業界全体の傾向を客観的に分析した情報として提供したところ、記事化されただけでなく、その後も定期的に意見を求められるようになりました。
3. 寄稿記事の活用
業界メディアの多くは、専門家からの寄稿記事を受け付けています。私たちが試したのは、創業者やCTOなど技術責任者による専門的な寄稿記事の提案です。最初は「取材を受けたい」とアプローチするよりも、「業界に役立つ情報を提供したい」というスタンスの方が受け入れられやすい場合があります。
最初の寄稿が掲載されると、その後の関係構築がスムーズになります。ただし、寄稿内容は自社宣伝ではなく、業界に価値ある情報提供を心がけることが重要です。私たちの場合、CTOが「スタートアップにおけるシステム開発の効率化手法」について寄稿したところ、専門性の高い内容が評価され、その後の取材依頼につながりました。
継続的な関係性維持のためのコミュニケーション戦略
記者との関係は一度構築したら終わりではなく、継続的に維持していくことが重要です。特にスタートアップの場合、大きなニュースが頻繁にあるわけではないため、ニュース以外でも関係を維持する工夫が必要です。
1. 定期的な情報提供と業界インサイトの共有
記者にとって価値があるのは、まだ一般には知られていない業界動向や市場の変化です。私が心がけていたのは、プレスリリースなどの公式発表だけでなく、業界の最新動向や市場の変化について、定期的に情報提供することでした。
例えば、海外の先進事例や、業界の裏話など、記者にとって「ネタになる」情報を、売り込みを目的とせずに共有します。「この情報は記事にするかどうかは別として、お役に立てばと思って」という姿勢で提供すると、徐々に信頼関係が構築されていきました。
2. 記者会食やオフレコ懇談会の開催
リソースが許せば、少人数の記者を招いた会食や懇談会を開催するのも効果的です。私たちのようなリソースの限られたスタートアップでは、大規模な記者会見は難しいですが、3-4名程度の記者を招いた少人数の懇談会なら実施可能でした。
このような場では、公式発表とは別に、「業界の今後の展望」「創業者の哲学」など、深い話ができます。一度、創業者の「失敗談と学び」をテーマに少人数の懇談会を開催したところ、その場では記事にはなりませんでしたが、後日「起業家の挑戦」という特集で取り上げていただけました。
3. 独占情報の戦略的な提供
良好な関係が築けた記者には、新サービスの発表などの際に「独占」や「先行」で情報提供するのも有効です。ただし、記者間のバランスや、そのメディアの影響力を考慮する必要があります。
私たちは新機能のリリース時に、普段から関係性のある業界メディアに1週間先行で情報提供し、その記者独自の視点で記事を書いていただく機会を作りました。記者にとっても「スクープ」になるため、丁寧に扱ってもらえることが多いです。この「Win-Win」の関係構築が、長期的なメディアリレーションの鍵だと実感しています。
危機管理とメディア対応の心構え
良好な関係を築いた記者であっても、ネガティブな情報を報じる可能性はあります。スタートアップ特有のリスク(資金調達の問題、サービスの障害など)が発生した際の対応も、事前に準備しておく必要があります。
私が経験した小さなサービス障害の際には、すぐに事実関係を整理し、対応策とともに関係のある記者に先回りして情報提供しました。「隠さず、正直に、迅速に」という姿勢が、結果的に大きな批判記事にならずに済んだと思います。
このように、メディアリレーションは良いニュースを伝える時だけでなく、危機的状況での対応も含めた総合的な関係構築が重要です。信頼関係があれば、厳しい状況でも公平に報じてもらえる可能性が高まります。
まとめ:持続可能なメディアリレーションのために
スタートアップのメディアリレーション構築は、一朝一夕にはいきません。私自身、最初は全く反応がなかった記者との間にも、地道な関係構築を続けることで、徐々に信頼関係を築くことができました。
メディアリレーション構築において最も大切なのは、記者の仕事と価値観を理解し、敬意を持って接することです。「記事にしてほしい」という一方的な願望ではなく、「読者にとって価値ある情報」という視点で考えると、自然と記者の心に響くアプローチができるようになります。
限られたリソースの中で全てのメディアと関係を築くことは不可能です。まずは自社の事業領域に関連する主要メディアを3-5社程度に絞り、そこから徐々に範囲を広げていくことをおすすめします。継続的な関係構築を通じて、メディアを味方につけることができれば、スタートアップの認知拡大に大きく貢献するはずです。➡️ 関連記事:PR担当者のためのメディアリレーション構築マニュアル|デジタル時代の3ステップ
成果測定と改善サイクル
広報・PRの効果って、どうやって測ればいいのか…。スタートアップの広報担当になってから、この問いには何度も頭を悩ませてきました。数字で効果を示せないと、経営陣からの理解も得られにくいですよね。私も最初は手探り状態でしたが、試行錯誤の末にようやく効率的な測定方法と改善サイクルを構築できました。今日はその経験をシェアします。
スタートアップ広報のKPI設定と測定方法
私が初めて広報担当になった時、「何を測れば良いのか」という基本的な疑問から始まりました。実際に試して効果的だったKPI設定のポイントをご紹介します。
まず重要なのは、自社のビジネスフェーズに合ったKPIを選ぶことです。シード期なら認知度向上やファンダー(創業者)のブランディングに注力し、アーリーステージなら商品・サービスの認知と理解促進、グロースステージなら市場でのポジショニング強化といった具合に、フェーズによって測るべき指標は変わってきます。
具体的には以下のような指標が役立ちました:
- メディア露出数: 単純ながら基礎となる指標
- 潜在顧客リーチ数: ターゲット層へのリーチを推計
- メディア掲載の質: 記事内での扱われ方を評価(単なる名前の掲載か、特集記事か)
- ウェブサイトトラフィック: PR施策との相関分析
- ソーシャルメディアエンゲージメント: 共有数やコメント数の変化
- 問い合わせ数変化: メディア掲載と問い合わせの相関関係
特に効果的だったのは、Google Analyticsでのリファラル分析です。どのメディアからの流入が多いか、その流入がどの程度コンバージョンにつながっているかを追跡することで、「どのメディアとの関係構築に注力すべきか」が見えてきました。
ただし、数値だけを追いかけるのは危険です。わが社では当初、「掲載数」だけを目標にしていた時期がありましたが、結果的に企業イメージにあまり貢献しない内容での掲載が増えてしまいました。そこで、質的評価も同時に行うことにしました。会社のメッセージや価値観がきちんと伝わる記事だったか、ターゲットオーディエンスに届いたか、といった視点です。
費用対効果の最大化手法
「限られた予算で最大の効果を」は、特にスタートアップにとって永遠のテーマですよね。私たちのスタートアップでも、最初は月5万円という非常に限られたPR予算からのスタートでした。そこで編み出した費用対効果最大化のテクニックをご紹介します。
1. 無料ツールの徹底活用
予算がなくても、以下のツールを組み合わせることで効果的な測定が可能です:
- Google Analytics(基本的なトラフィック分析)
- Google Alerts(自社名や業界キーワードの監視)
- Mention(ソーシャルメディアでの言及モニタリング)
- Canva(プレスキット用の無料デザインツール)
これらを使い始めて気づいたのは、高額なPRツールがなくても、創意工夫次第で十分な測定と分析ができるということ。特に初期段階では、こうした無料ツールの組み合わせで80%以上のニーズをカバーできました。
2. マイクロターゲティングの実践
大規模なPR活動より、特定のニッチなメディアや影響力のあるブロガーへの集中的なアプローチが、スタートアップには効果的でした。例えば、私たちのフィンテック系スタートアップでは、大手経済紙よりも、特定の金融テクノロジーに特化したオンラインメディアへのアプローチに集中したところ、狙ったターゲット層への浸透率が3倍になりました。
3. 測定結果の可視化とレポーティングの工夫
経営陣や投資家に広報活動の価値を理解してもらうため、データの可視化に力を入れました。単なる数値の羅列ではなく、「このPR活動によって生まれた具体的なビジネスインパクト」を示すことが重要です。
例えば、こんな形でレポートを作成しました:
- PR活動前後のウェブサイトトラフィックの変化グラフ
- メディア掲載と新規リード獲得の相関図
- 競合他社との露出量比較チャート
特に効果的だったのは、「この記事掲載によって○○社からの問い合わせが生まれ、△△円の商談につながった」といった具体的なストーリーを添えること。数字だけでなく、PRの具体的な成果を物語として伝えることで、経営陣からの理解と次回予算の獲得につながりました。
PDCAサイクルの回し方
広報活動は一度やって終わりではなく、継続的な改善が必要です。私たちのチームで実践して効果的だったPDCAサイクルの回し方を紹介します。
1. 適切な振り返りタイミングの設定
大きなキャンペーンごとの振り返りはもちろん、私たちは2週間に一度の「ミニ振り返り」を設定しました。これにより、大きな問題が発生する前に軌道修正できるようになりました。振り返りでは以下の点を確認します:
- 当初設定したKPIの達成状況
- 予想外に効果があった施策、期待はずれだった施策
- 次のアクションプラン
2. 失敗からの素早い学習と方向転換
私たち初期のスタートアップでは、テレビメディアへのアプローチに多大なリソースを投じたものの、まったく成果が上がらない時期がありました。そこで思い切って方針を変更し、業界特化のポッドキャストや専門メディアに焦点を当てることにしたところ、わずか1ヶ月で状況が好転しました。
このとき学んだのは、「失敗を早く認める勇気」と「方向転換のスピード」がPDCAサイクルを効果的に回す鍵だということ。毎週のデータ確認で「これは効果がない」と判断したら、すぐに別のアプローチを試す柔軟性が重要です。
3. 小さな成功体験の蓄積
大きな成果をいきなり求めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねていくアプローチが効果的でした。例えば:
- 業界インフルエンサー1人との関係構築
- ニッチなオンラインメディアでの1記事掲載
- 社内ブログの読者数10%増加
こうした小さな目標を達成するたびに「何がうまくいったのか」を分析し、次のステップに活かすサイクルを作りました。これにより、大きな失敗のリスクを減らしながら、着実にPR効果を高めていくことができました。
4. データドリブンな意思決定
個人的な感覚や好みではなく、データに基づいた意思決定を徹底しました。例えば、最初は「テック系媒体への掲載」を重視していましたが、データ分析の結果、実は「ビジネス系メディアからの流入ユーザー」のほうが成約率が3倍高いことが判明。このデータを基に、アプローチ先メディアの優先順位を見直しました。
広報活動の成果測定と改善は、正直なところ最初は手探り状態でした。でも、小さく始めて、データを見ながら少しずつ改善していくうちに、効果的なサイクルが回るようになりました。大切なのは、「完璧なPR戦略」を目指すのではなく、「常に改善し続けるPRプロセス」を作ることなんですね。
スタートアップの広報担当者として、限られたリソースの中でも成果を出していくためには、正確な測定と迅速な改善サイクルの構築が不可欠です。ぜひ皆さんも、自社のフェーズに合ったKPI設定から始めてみてください。どんな小さな一歩でも、継続的な改善を重ねることで、やがて大きな成果につながっていくはずです。
さいごに
スタートアップにおける広報活動は、まさに「少ないリソースでいかに大きな効果を生み出すか」という挑戦の連続です。私自身、中小PR会社でアシスタントコンサルタントとして働いていた頃、様々なスタートアップの広報支援に携わりましたが、その経験から言えることは、「正解は一つではない」ということ。それぞれの会社のフェーズや強み、創業ストーリーに合わせたアプローチが何より重要なんです。
地方の小さなテック企業の広報担当として苦労した日々を思い出します。予算はほとんどなく、大手メディアには相手にもされない…そんな状況で、いかに自社の魅力を伝えるか試行錯誤の日々でした。記者会見を開いても誰も来ないんじゃないか、という不安を抱えながらプレスリリースを配信した時のドキドキ感は今でも忘れられません。
でも、そんな中で気づいたのは、スタートアップならではの「小回りの利く」特性こそが、広報活動における最大の武器になるということ。大企業では決裁に何週間もかかるプレスリリースも、スタートアップなら社長と相談して即日配信できますよね。この機動力を活かして、時事的な話題に素早く反応したり、創業者自身の人間味あふれるストーリーを前面に出したりすることで、少しずつメディアの関心を引くことができるようになりました。
特に苦労したのはメディアリレーションの構築です。最初は全く繋がりがなく、送ったプレスリリースが読まれているのかすら分からない状態でした。そこで、まずは地方紙や業界専門メディアなど、比較的アプローチしやすいところから関係構築を始め、小さな掲載を積み重ねることで、少しずつ信頼を築いていきました。「いきなり全国紙を狙う」のではなく、「段階的にメディア露出を増やしていく」戦略がスタートアップには現実的だと感じます。
また、広報活動を進める中で痛感したのは、数字による効果測定の重要性です。限られたリソースをどこに集中させるべきか、常に判断を迫られるスタートアップこそ、しっかりとしたKPI設定と測定が不可欠です。「何となく良さそう」という感覚的な判断ではなく、「どのくらいの露出があり、それによってウェブサイトへのアクセス数や問い合わせがどう変化したか」といった具体的な数値を追うことで、効果的な施策とそうでないものを見極めることができます。
PRツールへの投資も悩ましいポイントでした。高額なプレスリリース配信サービスや監視ツールを使うべきか、それとも手作業で対応すべきか。私の経験では、初期段階では無料もしくは低コストのツールを組み合わせて活用し、成長に合わせて徐々に投資を増やしていく方法が現実的です。例えば、大手配信サービスを使う代わりに、自分でメディアリストを作成し個別にアプローチする方法は手間はかかりますが、その過程でメディアとの関係構築にもつながります。
広報担当として心がけたいのは、「自社の成長ストーリーを常に更新し続けること」です。創業時のビジョンは素晴らしいものでも、それだけでは長く注目を集め続けることはできません。製品アップデート、新しい顧客事例、資金調達など、会社の成長に合わせて常に新しい切り口を見つけ出し、それをストーリーとして紡いでいく作業が必要なんですね。
振り返れば、「これで完璧!」と思える広報活動などなかったように思います。常に試行錯誤の連続で、時には厳しい結果に落ち込むこともありました。でも、一つひとつの経験から学び、徐々に自社に合った広報のあり方を見つけていくプロセスこそが、スタートアップの広報活動の醍醐味なのかもしれません。
最後に、これから広報活動を本格化させようとしているスタートアップの皆さんへ。完璧を求めすぎず、まずは動き出すことが大切です。たとえ小さな一歩であっても、継続的な情報発信と関係構築を積み重ねることで、必ず成果は出てきます。そして何より、自社の本当の強みや独自性を見極め、それを誠実に伝え続けることが、長期的な信頼獲得につながると信じています。